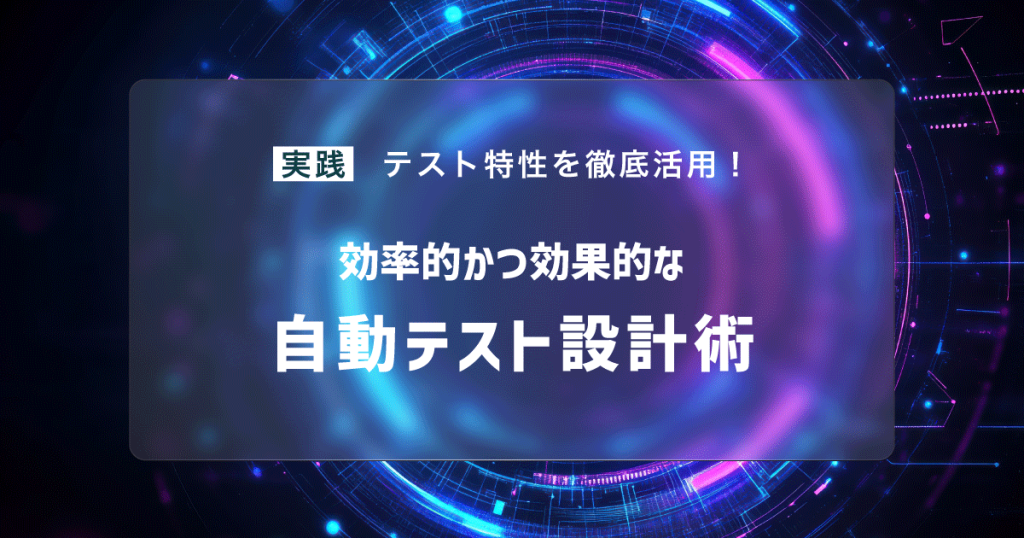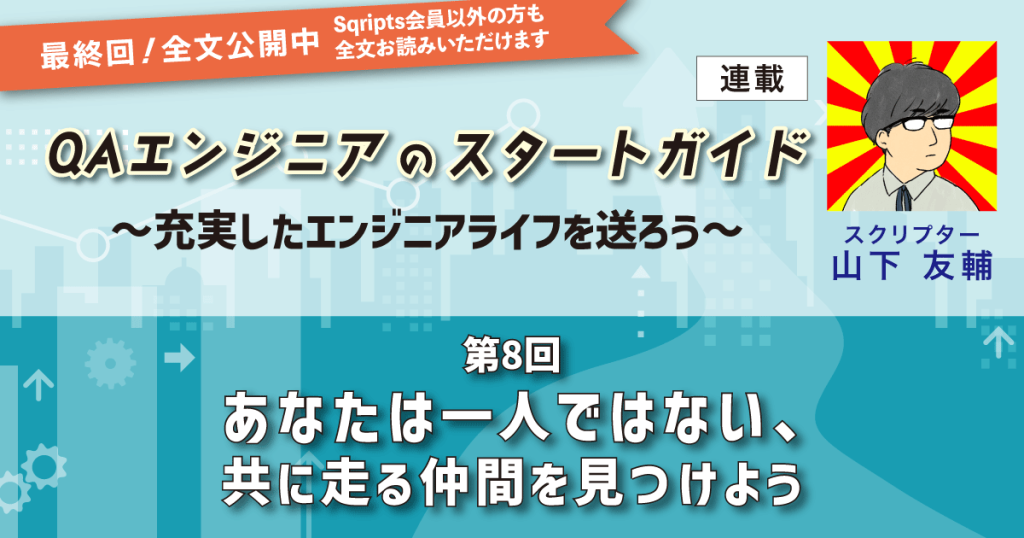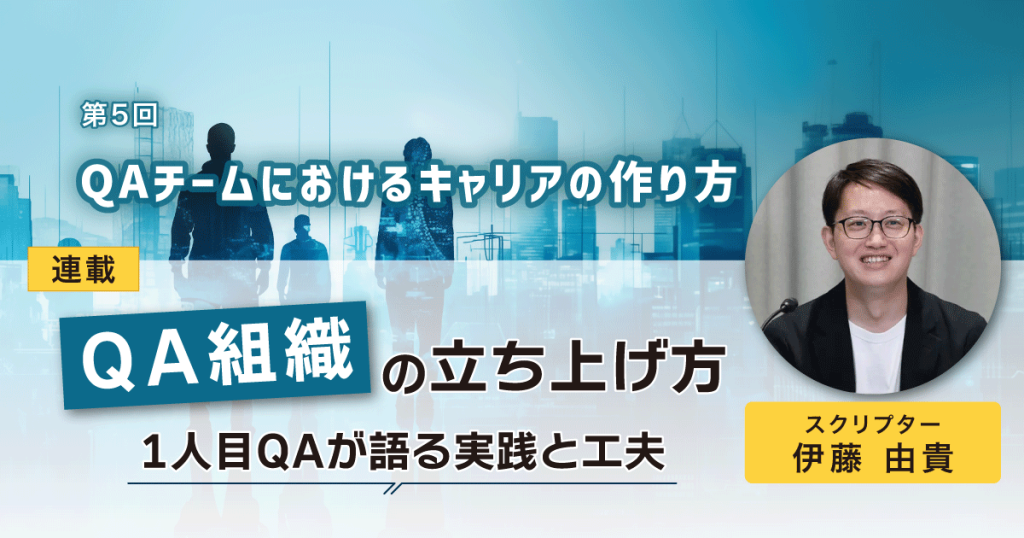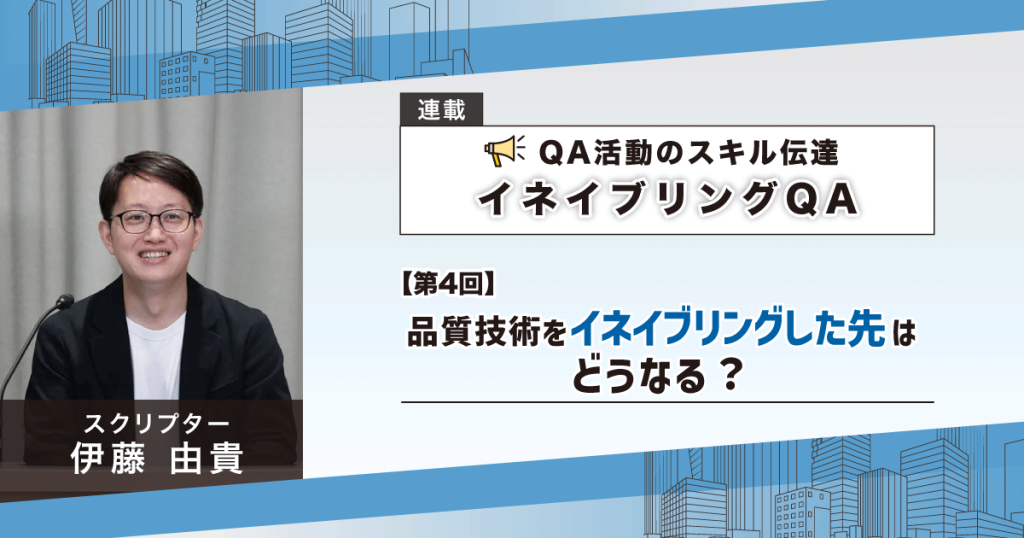
イネイブリングQAについての連載、第4回となる今回は、開発組織に対して品質技術をイネイブリングしたその先の姿について考えてみたいと思います。
<QA活動のスキル伝達「イネイブリングQA」 記事一覧>※クリックで開きます
前回の記事では、開発組織に品質技術を伝えていくために必要となる2つのスキルについて解説しました。
今回はその先のお話です。品質技術を伝えていったその先では、開発組織はどのような状態になっているのでしょうか。また、そのときQAはどのような位置づけになっているのでしょうか。
イネイブリングが進んだらQAエンジニアは不要?
QAエンジニアによるイネイブリング活動が進んでいき、開発者やPdMなどのロールが主体的に品質向上の取り組みを行えるようになった。そんな未来が訪れたとします。
イネイブリングQAとしてはまさに目指していた状態ですから、目的は達成したといえるでしょう。
しかし、開発組織がそのような、目指していた状態になったとき。QAエンジニアは何をするのでしょうか。安直に考えると、QAエンジニアの知識・スキル・業務自体をどんどん移譲していったら、QAエンジニアは不要になるようにも思えます。
もしかしたら、組織としても
- QAエンジニアの採用は大変だから、今いる最小人数で回せるようにしよう。できればゼロでもいいようにしよう。
- 派遣で来てもらっているテストチームの費用がかさんでいる。内製化の動きもあるし、段階的にテストチームをクローズしよう。
といった思惑があるかもしれません。その場合、イネイブリングによってQAのナレッジや業務を移譲していくことと、上記の思惑とがマッチします。イネイブリングQAは、がんばって自分たちの椅子を減らしているようにも見えてしまいます。
QAエンジニアのニーズはなくならない
私自身がQAエンジニアをやっていることもあり、ここからの話はポジショントーク的になってしまうかもしれません。しかしそれでも、QAエンジニアのニーズはなくならないのではないか、と思っています。
【第1回】イネイブリングQAとは何か?開発組織に品質文化を根付かせる第一歩|QA活動のスキル伝達「イネイブリングQA」 | Sqriptsにて、1999年出版の『Automated Software Testing』(邦訳:『自動ソフトウェアテスト 導入から、管理・実践まで 効果的な自動テスト環境の構築を目指して』)に登場するシステム方法論およびテスト(SMT)チームの活動について紹介しました。
再度引用します。
チームメンバーは、次から次へとさまざまなプロジェクト開発チームの主任と一緒に作業をして、知識移転、その他の活動を遂行する。
Automated Software Testing
あるチームで「イネイブリングしきった」となったとしても、他の開発チームでも同様の活動をできるかもしれません。ここは会社や開発組織の規模にも依存しますが、ある程度大きな会社であれば、数年でイネイブリングQAの活動がなくなることはないように思います。
他のポイントとしては、QA=品質保証に関連する領域が幅広いことも挙げられます。
たとえばスクラムマスターの資格を取得しているQAエンジニアの方は多くいらっしゃるように見受けられます。テストを行うなどわかりやすいQA活動とは異なるものの、開発組織がよりスムーズに回るための様々な取り組みを広義のQA活動と捉えれば、品質を高めるためにできること=QAエンジニアの業務スコープを大きく広げることができます。開発者だけでテストしてリリースできるようになったからQAエンジニアは不要、とはならず、他の貢献ポイントを見つけていく必要がありますし、それができるポジションだと考えています。
このように、
- イネイブリングする対象の開発者やチームが尽きない
- イネイブリングする範囲を広げることで、貢献できる点が尽きない
ことから、QAエンジニアのニーズはなくならないのではないか、というのが今時点での私の意見です。
実際に「イネイブリングしきってやることがなくなった」というQAエンジニアの声はまだ聞いたことがなく、むしろ次々と登場する新技術のキャッチアップ、QAエンジニアに求められる業務スコープの拡大など「やらなければならないことが多すぎて大変」というのが実際にQAエンジニアをやっている側の実感ではないでしょうか。
ただしQAへのニーズは変わっていく
QA活動のイネイブリングを行い、開発組織が一般的に良いとされるプラクティスを取り入れていったとします。そうなると、たとえばこれまでシステムテストに偏重していたテストが、テストピラミッドで表現されるように単体テストや結合テストにバランスよく分布することもあるでしょう。
その結果、システムテストを担っていたQA・テストチームの工数が従来より減り、より少ない人数で回せるようになる=QA・テストチームへのニーズが減る、といった動きが予想されます。
QAエンジニアへのニーズがなくなることはないだろう、と述べましたが、求められる内容は変化します。変化したニーズに対応していくことが、個々のQAエンジニアが生き残るために必要となってきます。(この点に関しては、次回の記事でも触れます。)
イネイブリングした先の姿を考えることが大切
本記事の冒頭で、
品質技術を伝えていったその先では、開発組織はどのような状態になっているのでしょうか。また、そのときQAはどのような位置づけになっているのでしょうか。
と書きました。
この点について、共通の正解はないだろう、と考えています。つまり、各組織におけるイネイブリングした先の姿・状態やQAの立ち回りについて理想像を設定する必要がある、ということです。
先に理想の姿があり、そこを目指してイネイブリングしていく、という順番です。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。