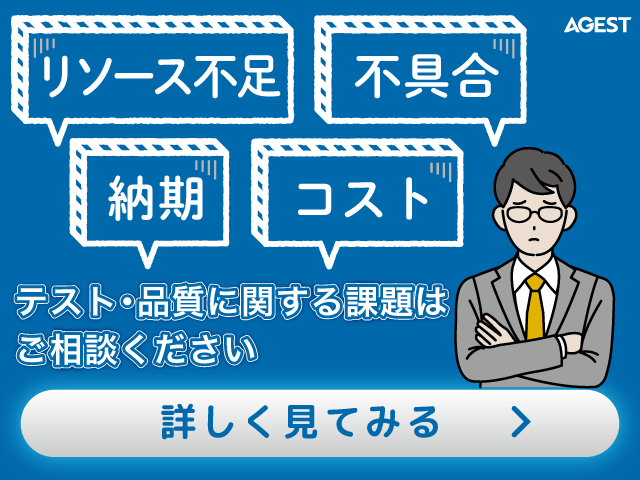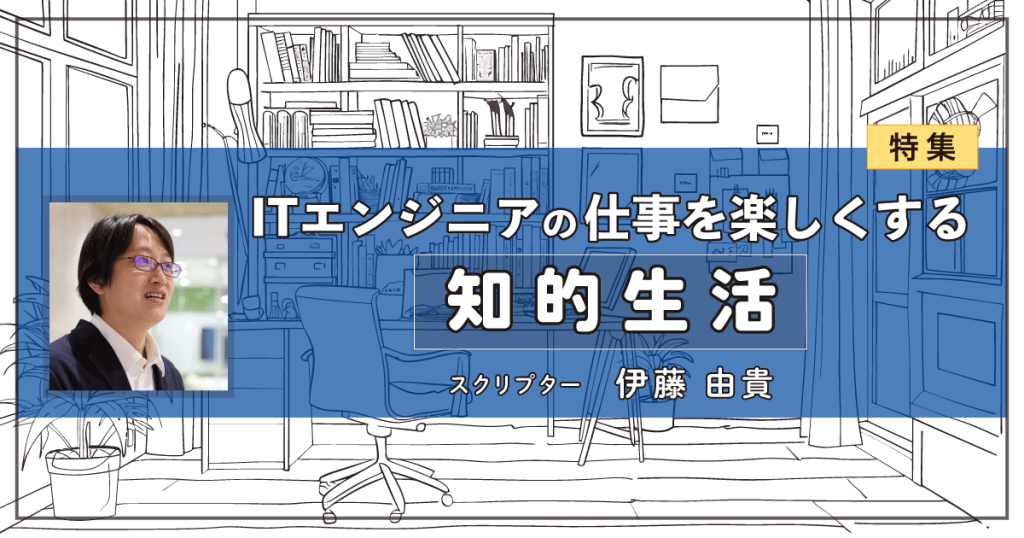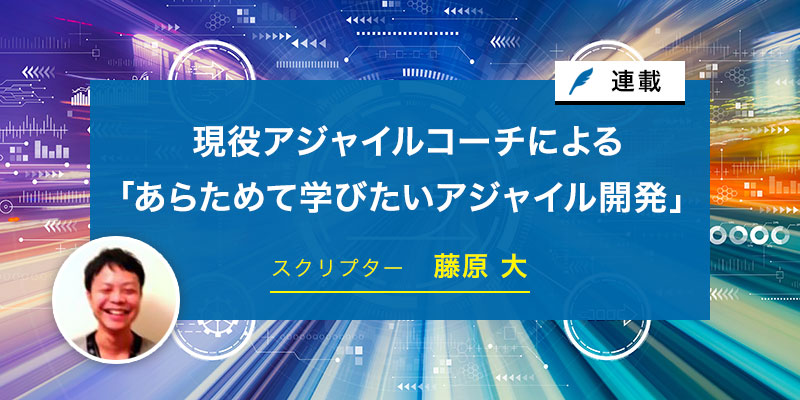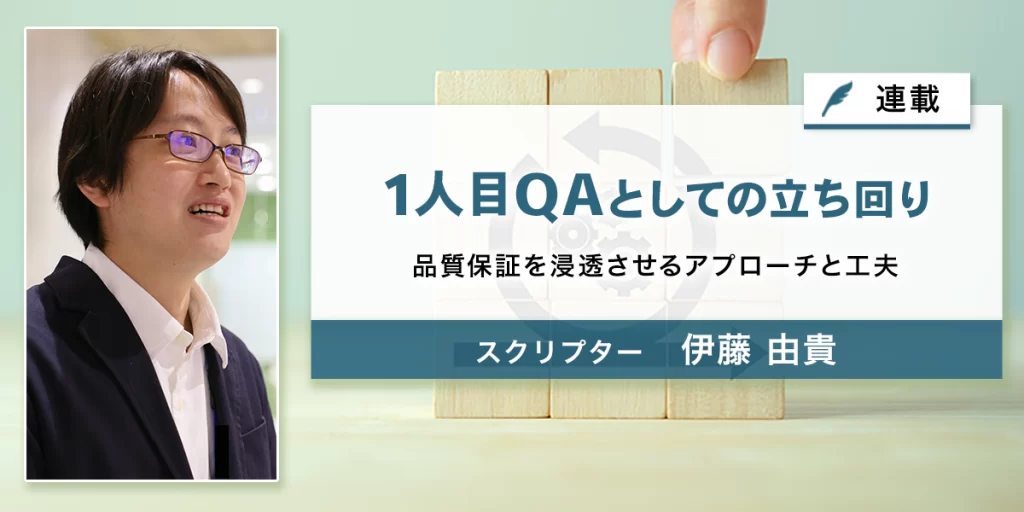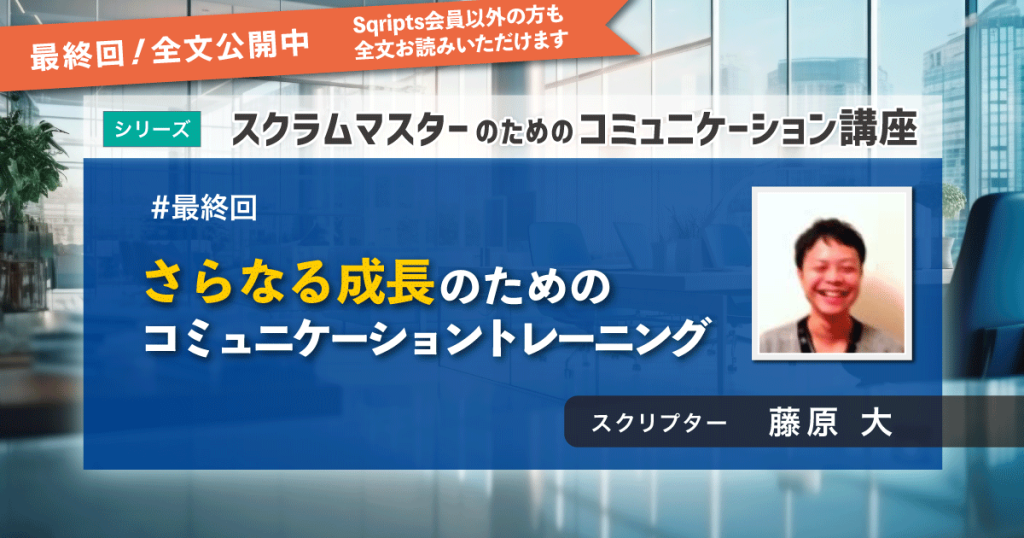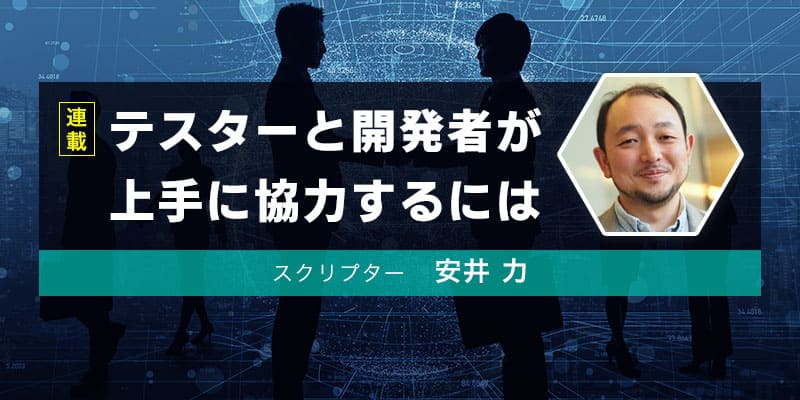
テスト駆動開発のスタイルを取り入れているもののテストのことはあまりよくわかっていないプログラマーと、テストへの熱い情熱をもちつつプログラマーの事情はわかっていないテスターとが、小さな障害の発見をきっかけとして出会い、役割の壁を崩しながら少しずつ協調するようになっていく、小さなお話です。
登場人物
プロ之 … プログラマー
テス緒 … テスター
前回、テス緒さんは現象を再現しようといろいろなテストケースを試しました。その話を聞いたプロ之さんは、テスト自動化の方法を教えつつ、テストについてもっと学びたいと伝えました。新たな手段を手に入れたテス緒さんですが、リーダーとの雑談でそれはよくないと言われてしまいました。
テストは全体のために

この会社では、チームのリーダーとメンバーは雑談のような1on1のような、気楽な会話の時間が定着しています。報告や指導というよりも、相談事だったり気になることをお互いに話したり、趣味の話やほんとうの雑談で終わることもよくあります。定期的にやっている人たちもいるし、不定期にときどき話す人もいます。
今回はテストチームのリーダーがテス緒さんに声をかけて、雑談をすることになりました。
「テス緒さん、おつかれさま。最近どう? 忙しいですか?」
「そうでもないですよー。むしろ余裕あるんで、前に気になったイシューの件を調べてます」
それを聞いたチームリーダーはちょっと黙り、表情は柔らかいままでしたが目が少し鋭くなりました。「そうだったんですか。それはちょっとよくないですね」
テス緒さんは驚いて、あわてて口を開きました。「あ、でもアサインされた機能のテストは遅れなくできてますし、残業もほとんどしてないですよ。開発チームにも迷惑かけてないと思います」
チームリーダーはテス緒さんの話を最後まで聞いた上で、ゆっくりうなずいてから言いました。「テス緒さんはアサインはこなしています。その点は大丈夫です。ただし、29分とか58分とかに業務終了するのは、ほとんど30分余計に作業してるのと同じですからね※1。お昼休みだって作業してるでしょう」
「えっ、それもわかるんですか」
チームリーダーは声を出して笑いました。「わからないですよ、監視してたりはしません。でもそうじゃないかなと思ったんです。テス緒さん熱心ですからね」
リーダーは続けました。「テス緒さんが、自分が見つけた違和感を粘り強く調べるのは素晴らしいと思います。テスターにはそうあってほしいんです。ただ、テストチーム全体や、プロダクト全体から見たとき、いまテス緒さんがそこに集中するのがベストなのか、そういう視点も持ってほしいんですよ。アサインした機能は、最近どうですか?」
そう言われてテス緒さんは思い出しました。ひとつの機能全体をアサインされたとき、ここをよく理解するとサービスの全体が見えやすくなるから、ただテストするだけでなく機能の有り様を深く把握してほしいと言われていたのでした。
「たしかに、あんまり調べてないです」テス緒さんはだんだんしょんぼりしてきました。
ここまで、テス緒さんとテストチームリーダーの会話の様子を見てきました。チームリーダーはテス緒さんの行動に反対しているわけではないようです。いっぽうで、いまは機能とサービス全体を学ぶことに集中してほしいという期待があります。また、ここで話題には上がっていませんが、プロダクトのリリースのタイミングなどではテストを速やかに、確実に進めるため全員が集中することもあるでしょう。
そう考えると、テス緒さんはプロ之さんを通じて開発チームとの関係性を築いてきましたが、それに加えてテストチームの中にいるテスターとしてどう振るまい、どう判断するといいのか、新たに学ばないといけないようです。チーム全体にとって大事なことは何か考えたり、それをチームに伝えたりすることです。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。