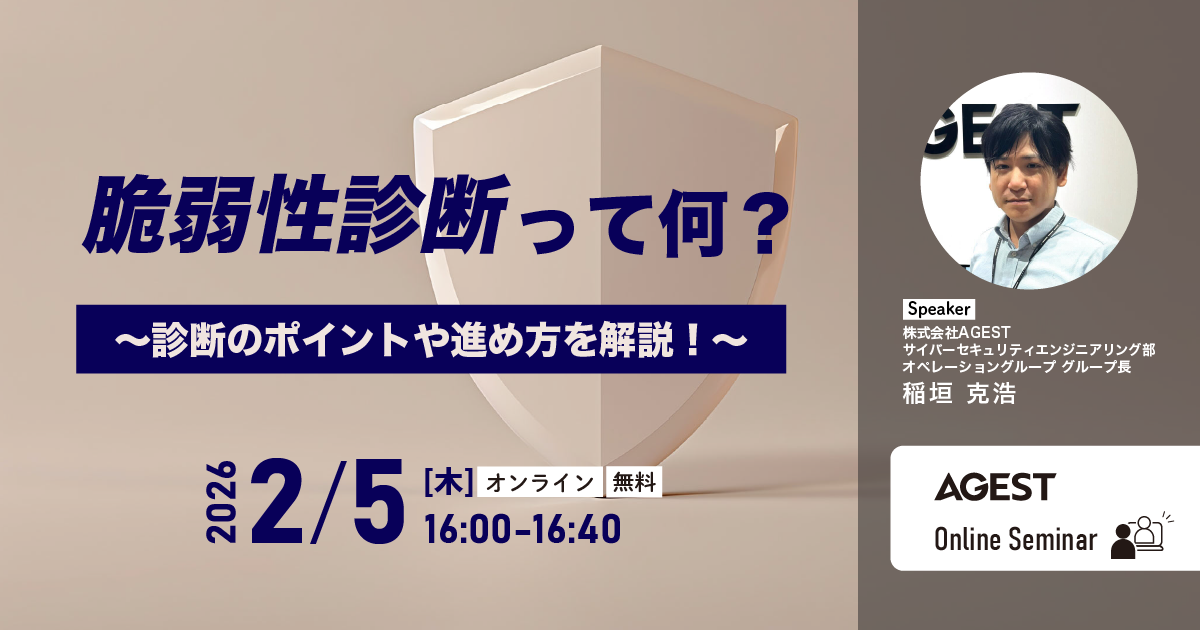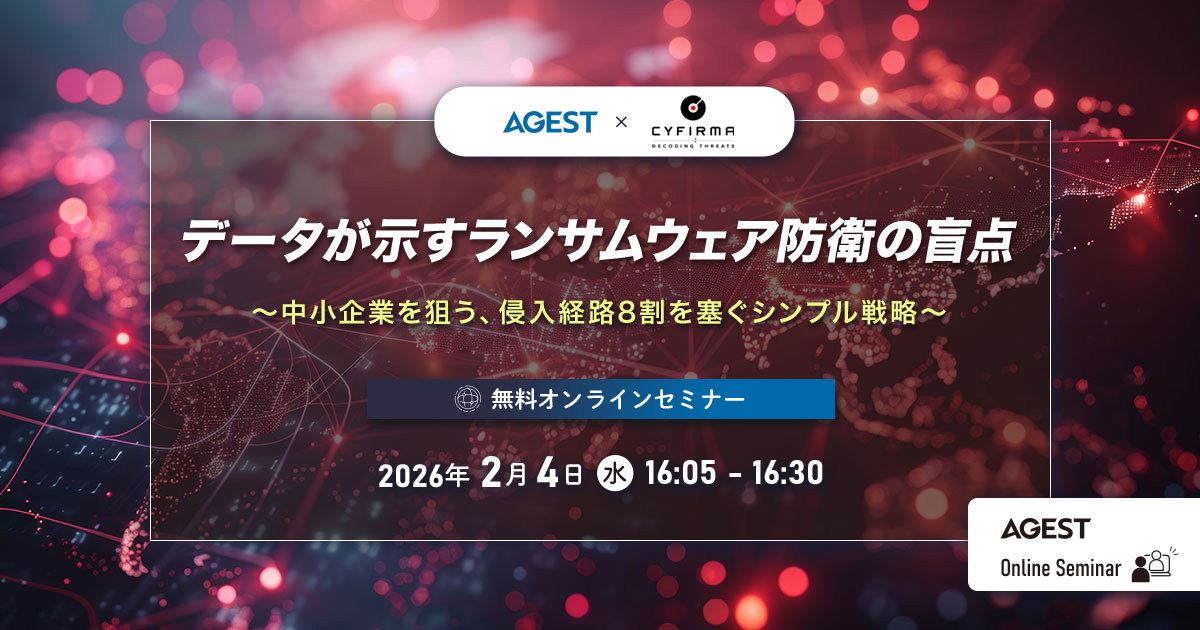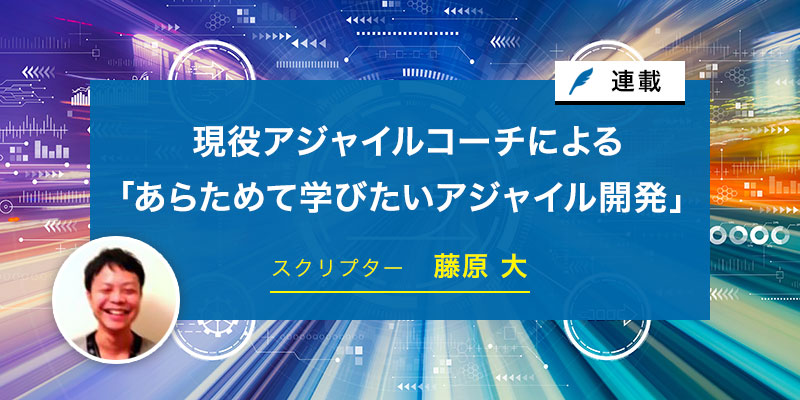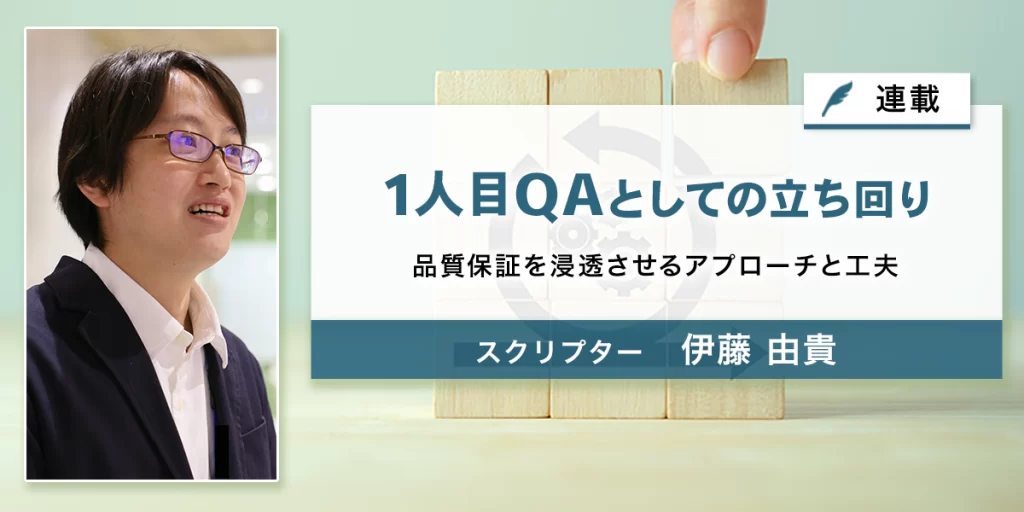現在は「VUCAの時代」と言います。VUCAとはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとったビジネスシーンで使われる言葉です。これら4つの言葉が表すとおり、「未来の予測が難しい状況」を表しています。
過去を振り返ると、使い古された言葉になりますが、高度経済成長時代に象徴されるように「作れば売れる」時代でした。しかし、VUCAという言葉が登場したように、現在は、「何が売れるかわかりにくい」状況に陥っています。ソフトウェア開発においても「何を作ればいいかわからない」時代になっています。
この連載では、現在やこれからの時代で求められるであろうソフトウェア開発における「品質」を再定義し、あるべき姿への道筋を示し、代表的なプラクティスなどを紹介しながら、アジャイルQA(アジャイルな品質保証、もしくは品質合意)活動や、具体的な手段としてアジャイルテスティングのあり方を議論していきます。
3回目のテーマは、アジャイルQAを実現するための具体的な方法を考えていきます。
アジャイルテスティング
ソフトウェア開発において、「QA(品質保証)」という言葉は広く知られています。よって筆者は、「アジャイル開発における品質改善活動」を「アジャイルQA」と呼び、QAと使い分けて使っています。
アジャイルQAに似た意味を持つ言葉として、「アジャイルテスティング」があります。アジャイルテスティングにはいろいろな流派があるようなので(参考:アジャイルテスティング問答 – 千里霧中)、ここでは「アジャイル開発をうまく支えるためのテストや品質保証のアプローチ」としています。
参考記事にもあるように、アジャイルテスティングはプロセスや方法論ではなく、テストや品質に関わるエンジニアのマインドセットやチーム文化、本質的な価値や原則と言えます。
よって、具体的なプラクティスが定義されているわけではないので、関連する書籍や文献を読むだけではマインドセットや精神論で思考停止してしまう可能性があります。
アジャイルテスティングが価値や原則であるならば、それらを実現するためのプラクティスが必要になります。「アジャイルQAはこうはじめればいい」や「これをやればアジャイルテスティング」といったものを定義するのは難しいですが、いくつかの現場でアジャイルQAを目指していく上で、共通解のようなものが見えてきたので、それらをまとめてみようと思います。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。