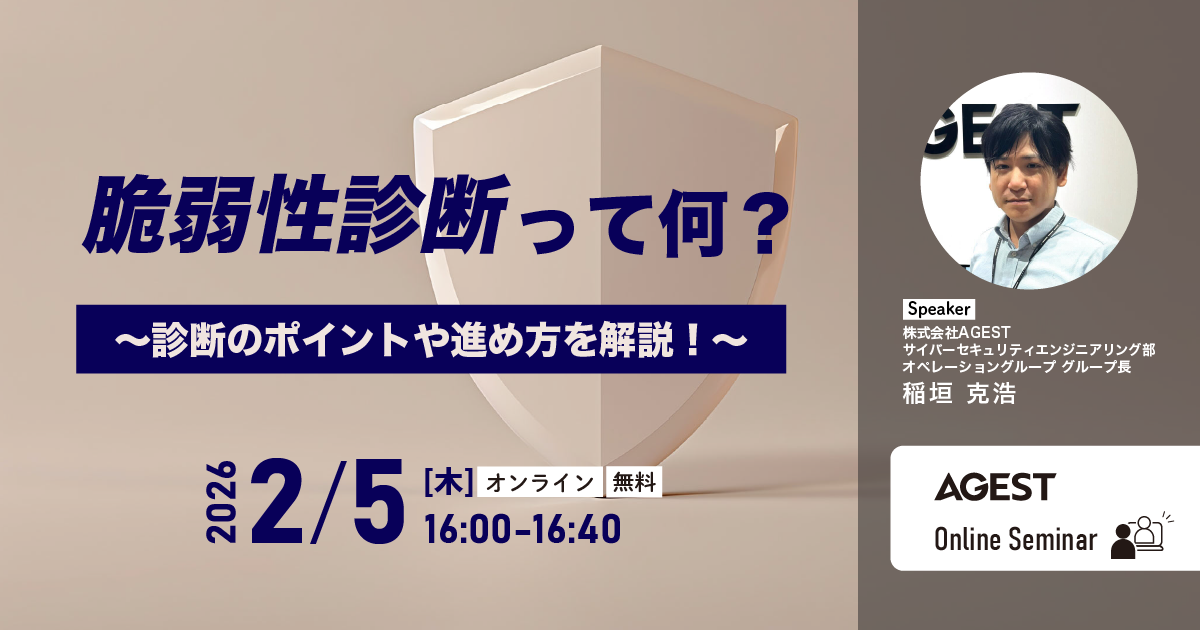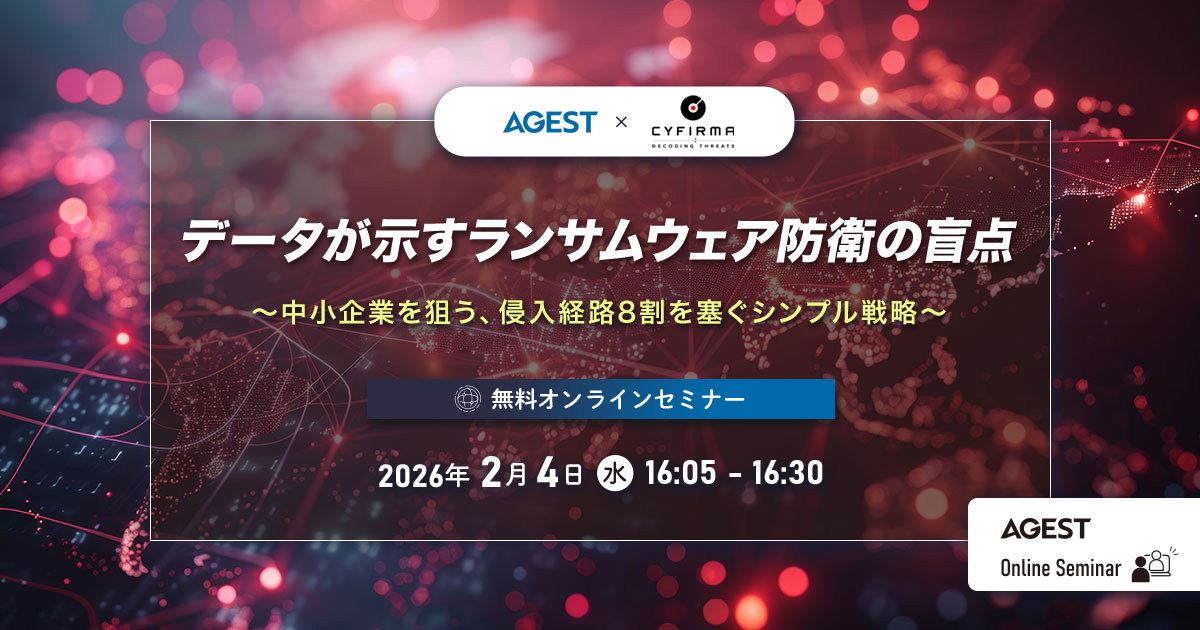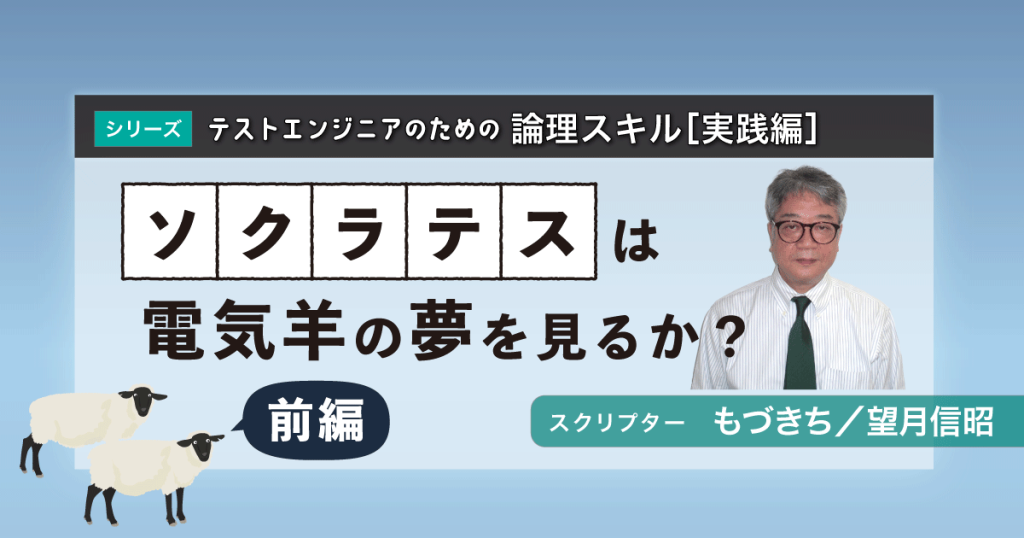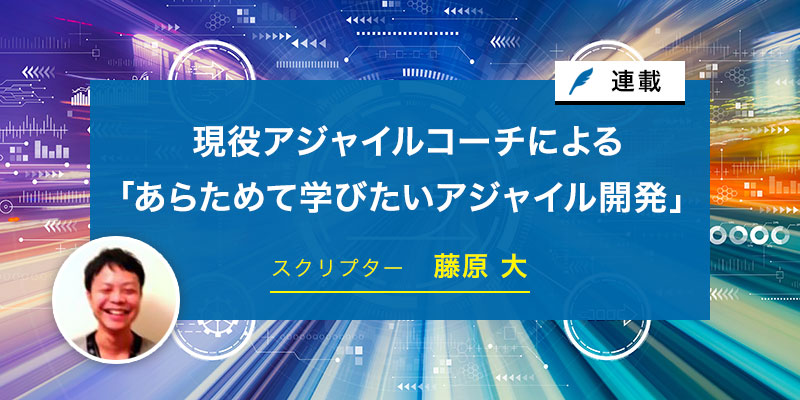
この連載は、登場して20年が過ぎ、成熟期を迎えつつある「アジャイル開発」を解説します。アジャイル開発については、世の中にたくさんの書籍や情報があふれていますが、アジャイルコーチとして10年以上の現場経験をもとに、あらためて学び直したい情報を中心にまとめていきます。
第9回目のテーマは、「エクストリーム・プログラミング(XP)」です。
この内容はUdemyで公開しているオンラインコース「現役アジャイルコーチが教える!半日で理解できるアジャイル開発とスクラム 入門編」の内容を元にしています。
価値・原則・プラクティス
XPの話をする前に、価値・原則・プラクティスを解説します。スクラムやXPのように、世の中にはさまざまな開発手法がありますが、それぞれの手法には価値・原則・プラクティスが定義されてるケースが多いです。これらがどういった意味を持つのかを見ていきましょう。
まず、価値とは、「何を考え、何を行うのかを判断するのに使用する基準」です。開発手法が持つ価値観なので、開発手法が大切にしていることが価値としてまとめられています。この価値があることで、開発手法を利用する人は、「自分たちは、この開発手法の価値を満たしているだろうか?」と判断ができます。
価値はふんわりした言葉になるので、じゃ、どうやったらその価値を実現できるのか?がわかりにくいと思います。たとえば、アジャイルマニフェストの一例をあげると、「個人と対話を」という価値がありますが、これをどう実現すればいいか? これだけではそこまでわかりません。
また、価値だけだと間違った判断になってしまう可能性があります。たとえば、アジャイルマニフェストだとコミュニケーションに価値を置いてますが、「コミュニケーションを重視したいから1000ページのドキュメントを書こう!」となると、ドキュメント作成に時間がかかりすぎて、アジャイルな開発とは言えません。そこで登場するのが原則です。
原則は、価値とプラクティスを支える橋のような存在です。原則は、「具体的な指針」なので、具体的に何をすればいいかわかりやすいものになっています。
アジャイルマニフェストの原則を見てみると「顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します」というのもあります。この原則を守って、価値を実現していこうというものです。
先程の例にでてきた「1000ページのドキュメントを書こう!」の場合、「フェイス・トゥ・フェイスで話をする」や「シンプルさ(ムダなく作れる量を最大限にすること)が本質です」という原則にマッチしません。マッチしないので、価値を満たさない可能性のあるアクションだと気がつけます。
プラクティスは、価値へと向かう原則をより具体的にしたものです。アジャイルプラクティスとも呼ばれます。プラクティスには「実行」、「練習」、「習慣」という意味があり、アジャイル開発だと「アジャイルになるための習慣」という表現がふさわしいかもしれません。アジャイルプラクティスをやればアジャイル開発になる!とはかぎりませんが、少なくとも価値へと続く橋のような存在になります
エクストリーム・プログラミング
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。