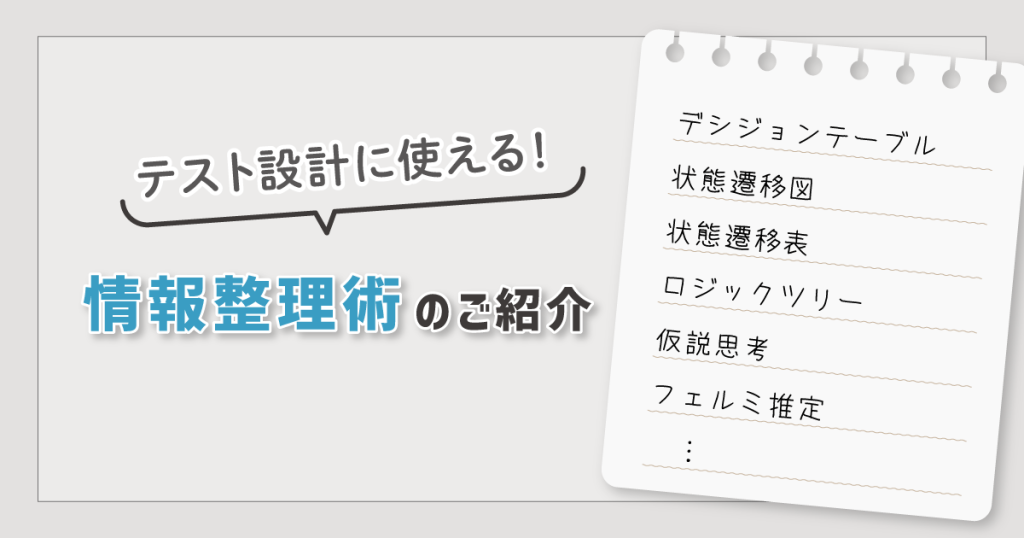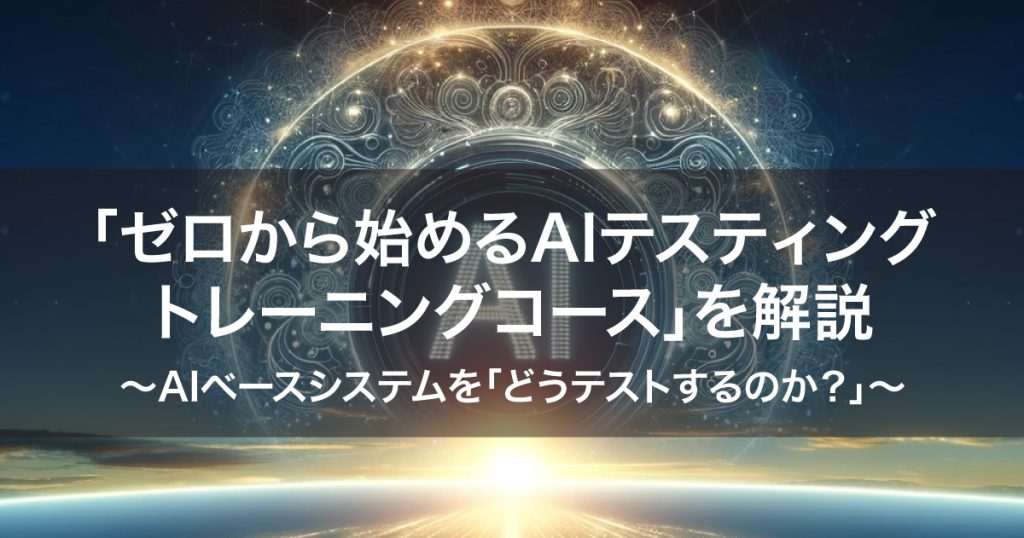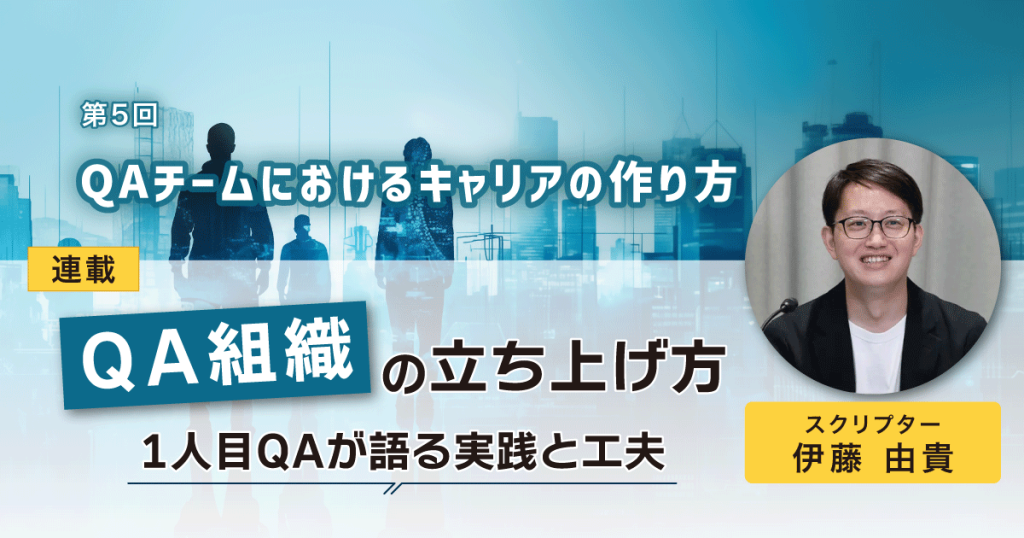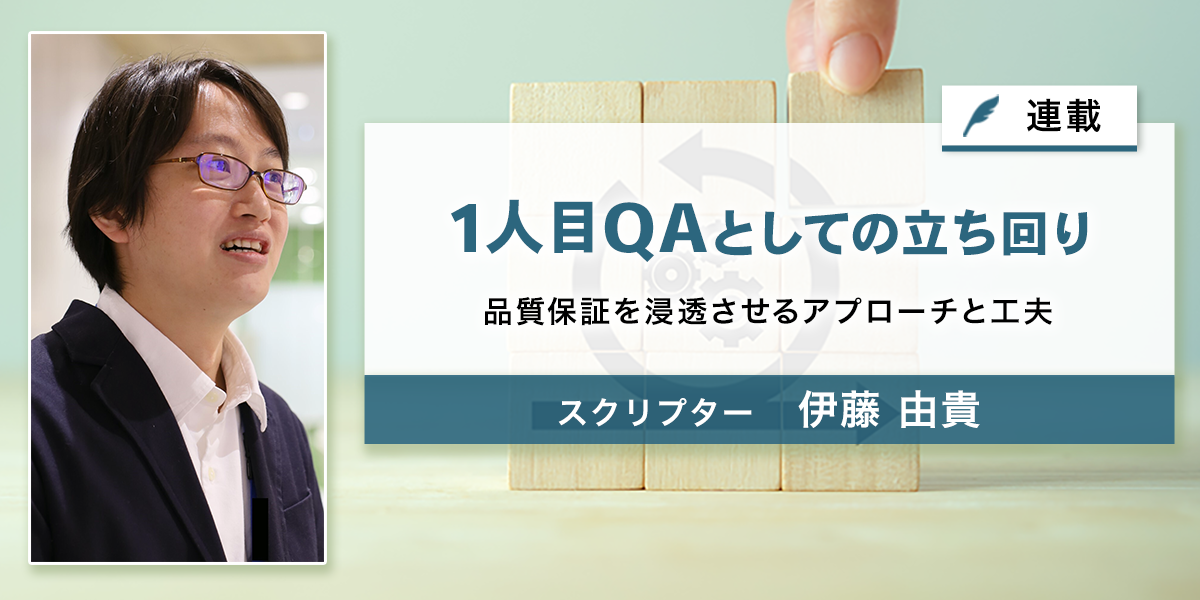
「1人目QA」というワードを、2020年ごろからよく聞くようになりました。
もちろんそれ以前から、組織の中で1人目のQAとして活動をされてきた方はたくさんいました。
しかし、QAエンジニアという職種の認知が広まったことで「いままでQA専門の人は居なかったけど、ウチにも要るよね」と思いはじめた会社が多くなり、採用募集や実際に1人目QAとしてお仕事をする方も増えたように思います。
私自身も、現在は1人目のQAとして試行錯誤をしている身です。
そこで、本記事からは“1人目QAとしての立ち回り”シリーズとして、1人目のQAに求められていること、実際にやってみて大事だと思ったことなどをお伝えしていきます。
なお、本記事では「QAエンジニア」を指して「QA」と表現します。
<1人目QAとしての立ち回り 連載一覧>※クリックで開きます
【第1回】1人目QAの位置づけと、開発組織へのアプローチの仕方
【第2回】組織に品質保証を浸透させるアプローチ
【第3回】品質保証やQAエンジニアを知ってもらうための取り組み
【第4回】1人目QAのスタートは開発組織の現状把握から。やるべきこと・把握すべきこと。
【第5回】1人目QAアンチパターン
1人目QA、とはなにか
まずはタイトルにもある「1人目QA」がそもそも何なのか、から考えてみましょう。
会社の1人目なのか、部署の1人目なのか、などは組織によってバラバラですが、共通するのは「前任者や同僚のQAが居ない状態」に新たに入ってきたQAエンジニアという点です。
前任者や同僚が居ないということは、
- テストや品質保証を開発者が試行錯誤しながら行っている、テストや品質保証の体制が整っていない
- QAの具体的な役割やロール設定がない
ということです。つまり、1人目QAはプロダクトのテストや品質保証業務と並行して、これらを決める・つくることも担う存在、といえます。
需要が増えている1人目QA
冒頭にも触れたように、2020年ごろからX(旧Twitter)上でも1人目QAに関する言及が増えてきており、求人サイトでも「QA立ち上げメンバー」や「1人目QA」などを募集する企業を目にするようになりました。
要因はさまざま考えられますが、そもそもの「QAエンジニア」というロールの認知・必要性の理解が進んできているため、募集する企業が増えた、と考えられます。それに伴って、「今はQAエンジニアやQA専任の組織はないけれども、新たに立ち上げをしたい」という企業も増えてきました。
QAチームをつくるうえで、1人目のQAはとても重要です。
そのチームや組織のカルチャーを創る存在でもありますし、組織におけるQAや品質への期待を把握しつつゴールとタスクを具体化しながら進めていく、という高難度の仕事を担うことになります。
開発組織へのアプローチの仕方
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。