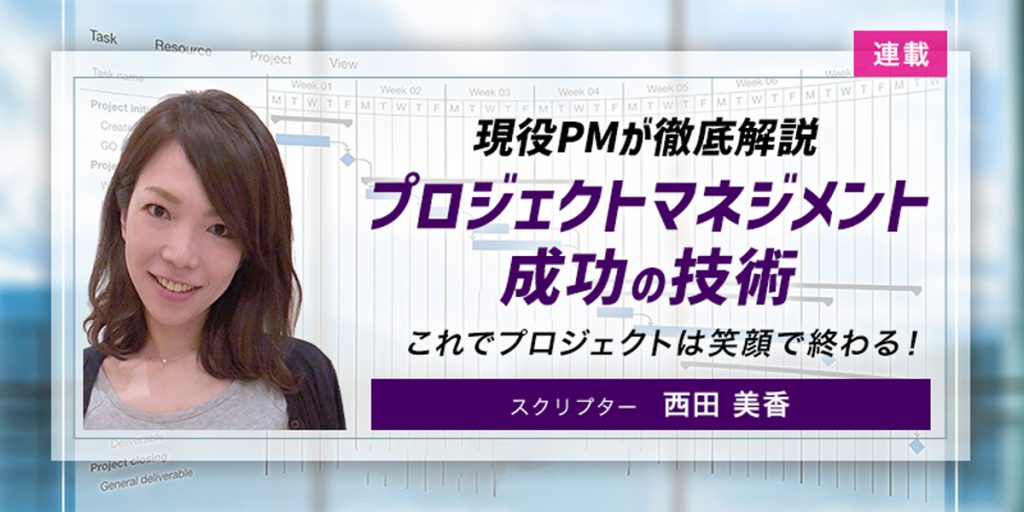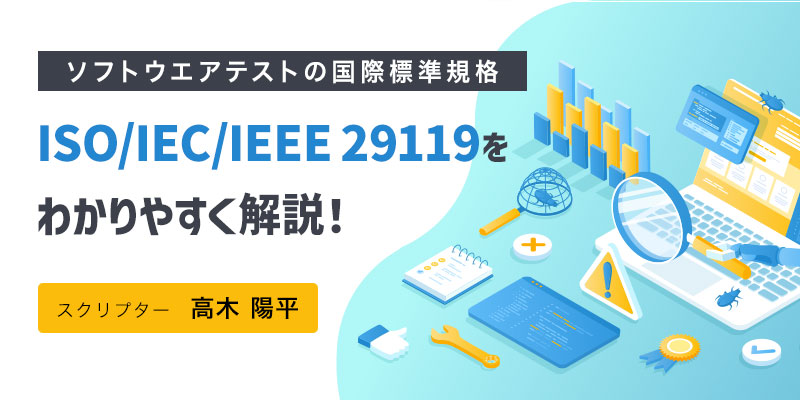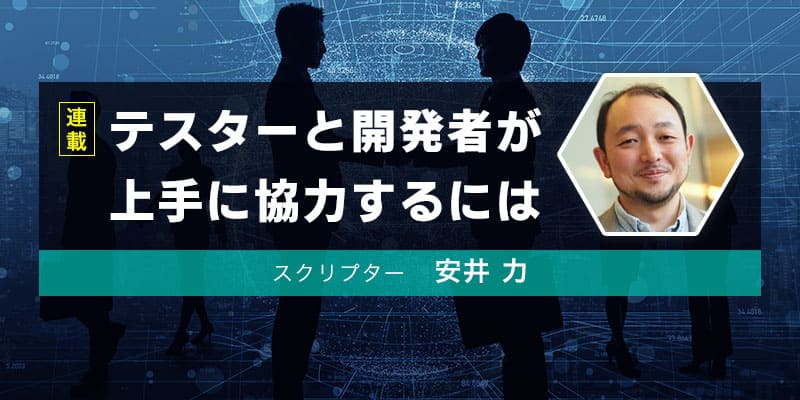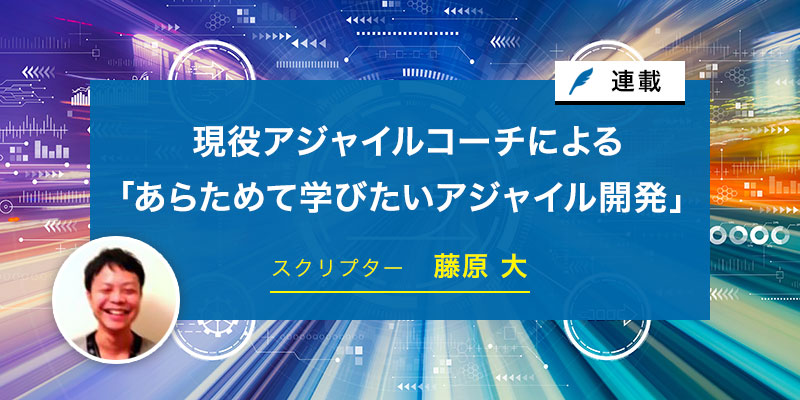
この連載は、登場して20年が過ぎ、成熟期を迎えつつある「アジャイル開発」を解説します。アジャイル開発については、世の中にたくさんの書籍や情報があふれていますが、アジャイルコーチとして10年以上の現場経験をもとに、あらためて学び直したい情報を中心にまとめていきます。
第11回目のテーマは、「エクストリーム・プログラミング(XP)」です。前回は原則と基礎プラクティスを解説をしたので、今回は応用プラクティスを解説します。
この内容はUdemyで公開しているオンラインコース「現役アジャイルコーチが教える!半日で理解できるアジャイル開発とスクラム 入門編」の内容を元にしています。
XPの応用プラクティス:実顧客の参加
ひとつめは「実顧客の参加」です。第1版では「オンサイトユーザー」でした。
ユーザー VS チームという構図をなくすためには、ユーザーを巻き込んだ開発が必要です。可能であれば、ユーザにもチームの一員として入ってもらうのも手です。
顧客の参加方法もいくつか選択肢があるはずです。たとえば、定期的に開発現場に来ていただくこともできますし、客先にスペースを作ってもらってそこで作業することもできます。
どちらにせよ、顧客と開発を切り離してはなりません。
XPの応用プラクティス: インクリメンタル配置
2つ目が「インクリメンタル配置」です。
配置というのは成果物を環境に配置する「デプロイ」を指しています。当時はデプロイという言葉が一般的ではなかったのだと思います。XPではイテレーションごとに成果物をインクリメンタルにデプロイを繰り返します。
正確に訳すなら継続的デプロイメントですが、今風な言い方にするなら継続的デリバリー(CD: Continuous Delivery)が近い言葉でしょう。つまり、デプロイやリリースの自動化です。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。