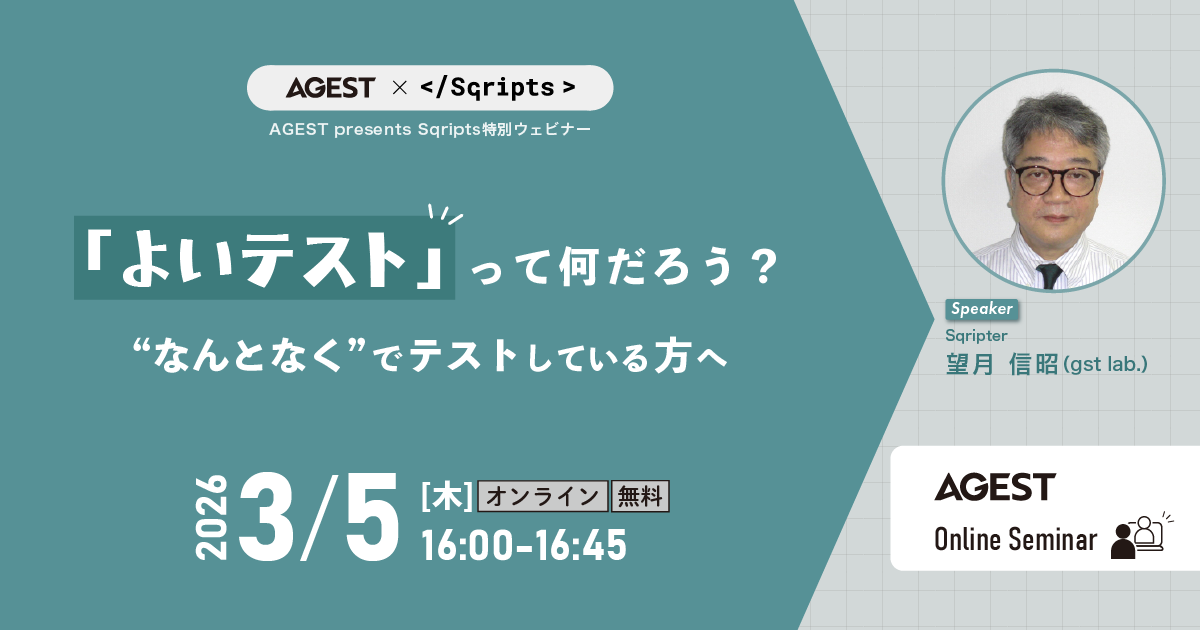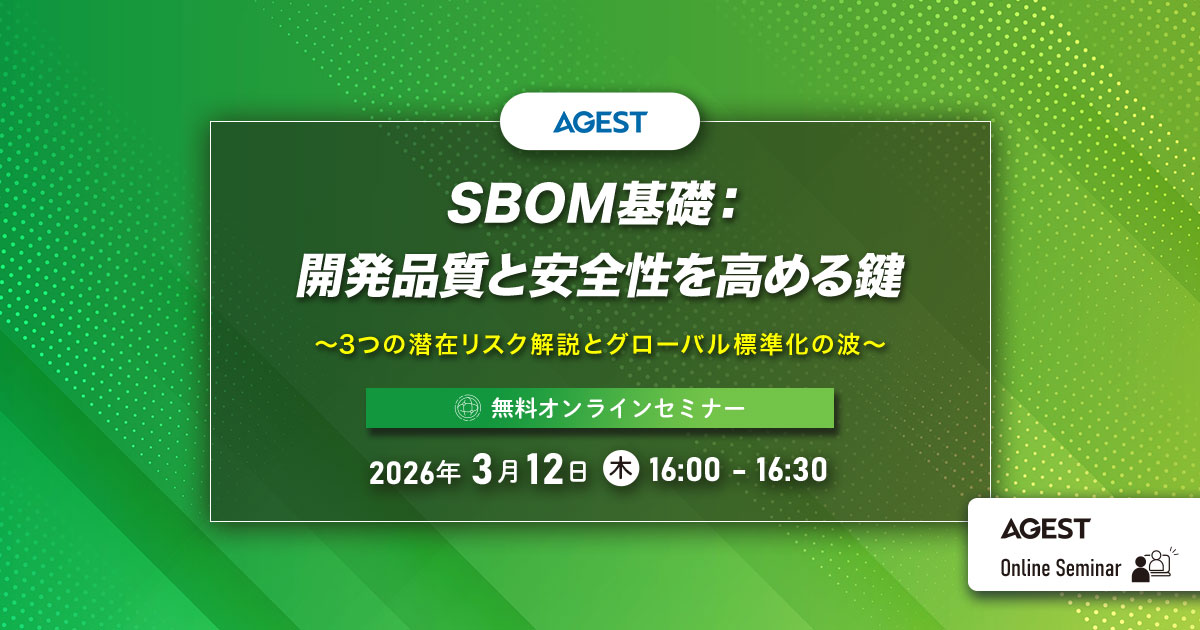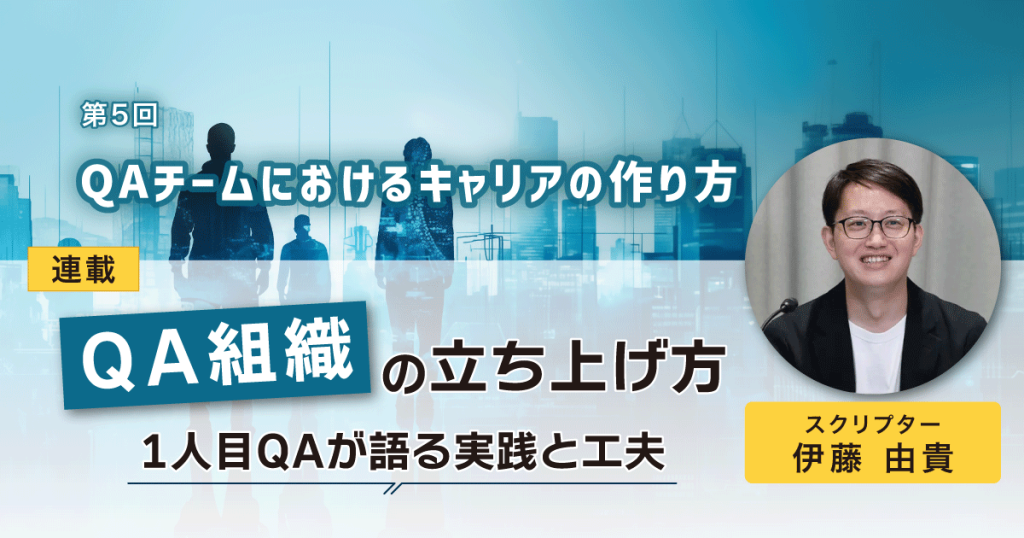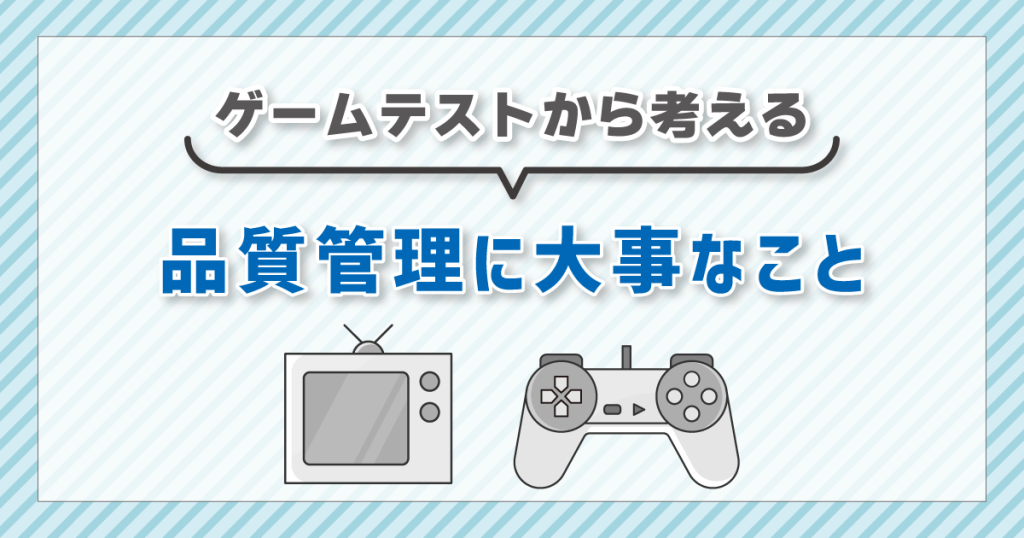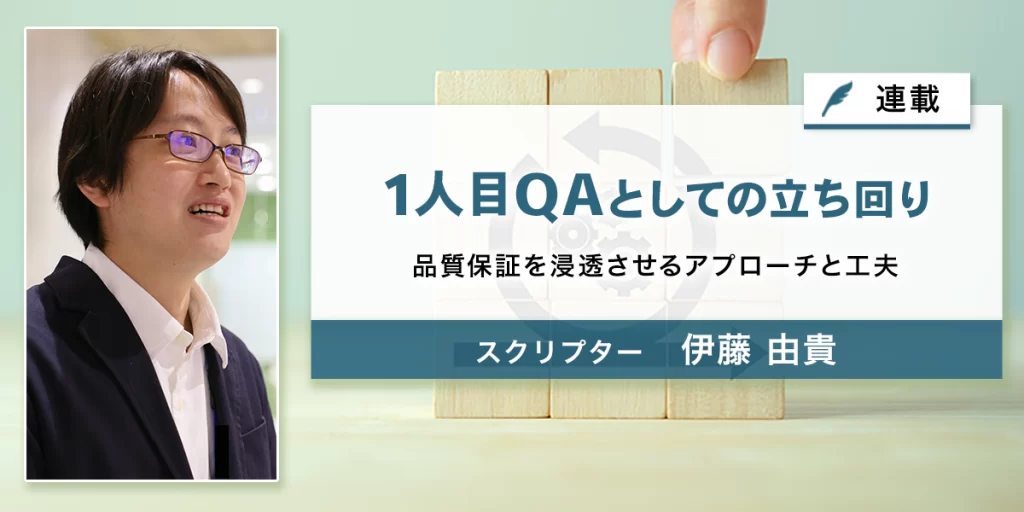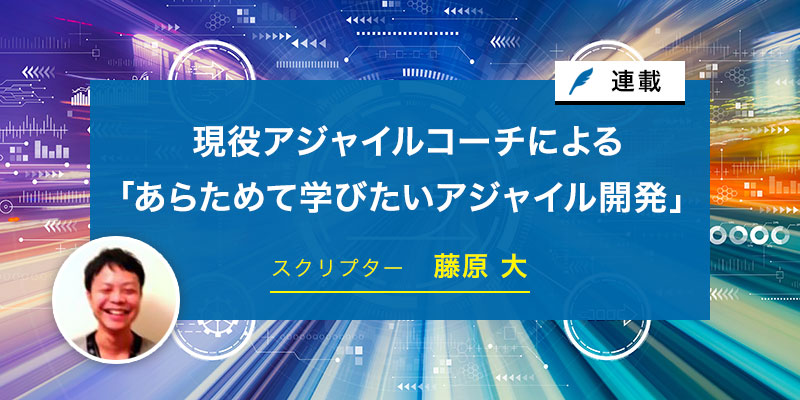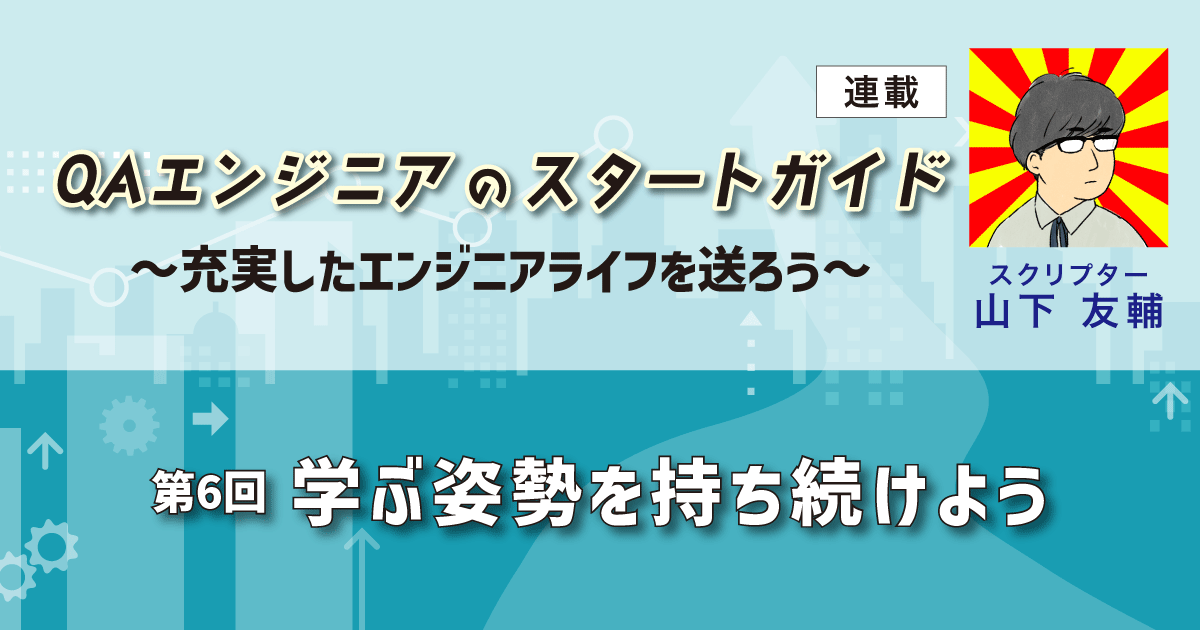
この連載では、ソフトウェア開発のQAエンジニアとして働き始めた皆様に向けて、私の実体験をもとに「こんなことを知っておけばよかった」という、ちょっとした気づきを共有します。
一緒にソフトウェア開発のQAエンジニアとしての充実したエンジニアライフを築くためのヒントを探っていきましょう。
<QAエンジニアのスタートガイド 記事一覧>※クリックで開きます
本記事ではエンジニアとして重要な課題である「学ぶこと」について解説します。
学ぶことは大切です。ITという分野は技術やトレンドの移り変わりが激しく、常に最新の知識をアップデートしていく姿勢が求められます。
また、ITエンジニアは、学ぶことでさらにキャリアを飛躍できる可能性が高いです。
私が過去に経験していた営業職では、「勉強してもなかなか結果につながらない」ということがありました。もしかしたら他の職種でも同じような状況があるかもしれません。
一方で、ITエンジニアは学んだ知識をすぐに試せる特徴があると実感しています。また、世の中で広く知られている知識の多くは、現実のプロダクト開発の貢献につながるような、実践的なものがたくさんあるとも思います。
なので、前向きに学び、それを普段の業務で実践することは充実したエンジニアライフに繋がると考えています。
学び方は、学校教育や受験勉強など、これまでの人生でたくさん経験してきたのではないでしょうか。
しかし、実際に働いていく中では、学生時代と同じように学べないことがあると思います。
本記事では、社会人として、学びを継続することの考え方やコツを伝えていきます。
さまざまな方法で学習する
学習の仕方を学ぶ
社会人になると、1日のほとんどを学びに使っていた学生時代と状況が異なります。
もしかしたら、仕事や家庭の事情で、以前と同じようには学習できないかもしれません。
これらは時間的な要因だけでなく、脳の成長や、経済的な環境の変化にも影響を受けているのだと考えています。
そのため、社会人、そしてエンジニアとしての学び方を身につける必要があります。
具体的な学習の方法は、様々な書籍で言及されていますので、ここでは個別の学習方法について言及しないでおきます。
学習の仕方を学ぶには、以下の本をおすすめします。
- エンジニアの知的生産術(西尾泰和 著/技術評論社)
- 一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方(加藤俊徳 著/サンマーク出版)
- 独学大全(読書猿 著/ダイヤモンド社)
学習方法には様々なものがあり、具体的にどうやって学ぶかは、自身で考える必要があります。
重要なのは、一人一人に合った学習方法があり、「これが最高」というベストプラクティスは存在しないということです。
アウトプットを通じて学ぶ
個人的にいい学習方法だと思っているのは、アウトプットを通して学ぶことです。
ご自身が使用するナレッジマネジメントツールへの記録、SNSやブログへの発信、イベントへの登壇、普段の仕事での実践などです。
しかし、SNSやブログを通してパブリックな場にアウトプットすると、批判を受けてしまう可能性もあります。外部に向けてのアウトプットはいい面もあれば悪い面もあります。
それでもアウトプットをおすすめする理由は、自分の記憶に頼らなくても、ネット上から自分で検索して思い出すことができるというメリットがあることです。
アウトプットを通じて、自分の力を自分の外に蓄えておくことが可能になるのです。
「テスト」を通じて学ぶ
QAエンジニアとして、様々なソフトウェア開発の言語やフレームワークを学ぶことがあると思います。
そういった場合に私は「どうやったらテストできるかを考える」ことを通して学んでいます。
テストとは試験ではなく、ソフトウェアテストです。
ソフトウェアテストは、そのプログラムの呼び出し、処理、アウトプットなど、ソフトウェアの概観を理解するのに重要な要素が詰まっています。
プログラミングを苦手だと感じているQAエンジニアは少なくありません。
そんな人は一度、「この言語やフレームワークはどのようにすればテストできるのだろうか」から考えてみることをおすすめします。
習慣を味方につける
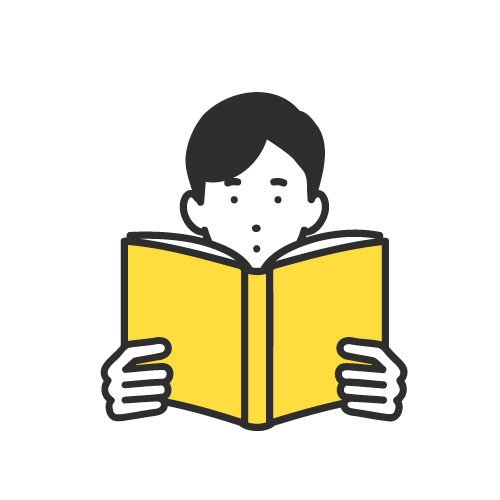
社会人になると、様々な年齢や経験を持った人と比較されます。
そのため、学生時代のような、「同じ世代が同じスタートを切って比べる」ような経験からマインドをチェンジする必要があります。
早く到達することより、むしろ長い時間をかけてでも高い能力に到達することで、メリットを享受できることを理解することです。
だからこそ、長期的な視点で学習に取り組むことは大切だと思います。
「習慣にできるかどうかはその人の性格による」と考えている人もいるかもしれません。実際に私もそう考えていました。
しかしながら、習慣化にもまた技術があり、習熟することが可能なのです。
小さな習慣から始める
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。