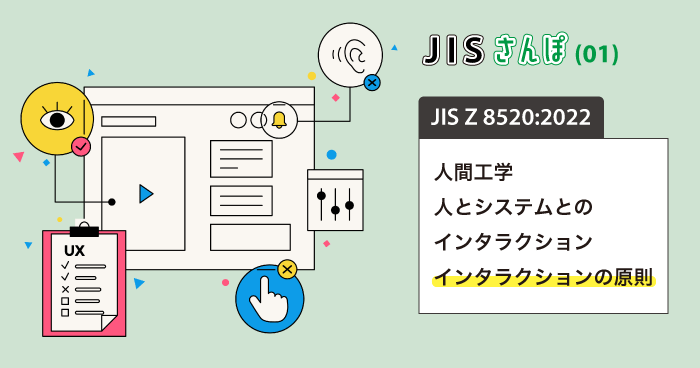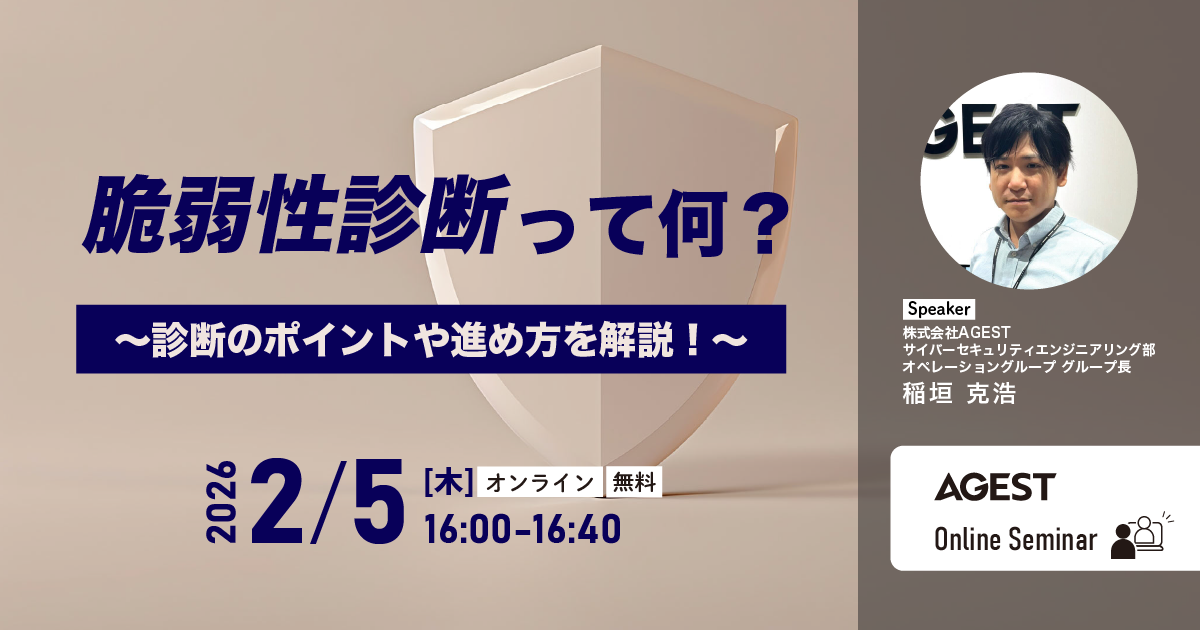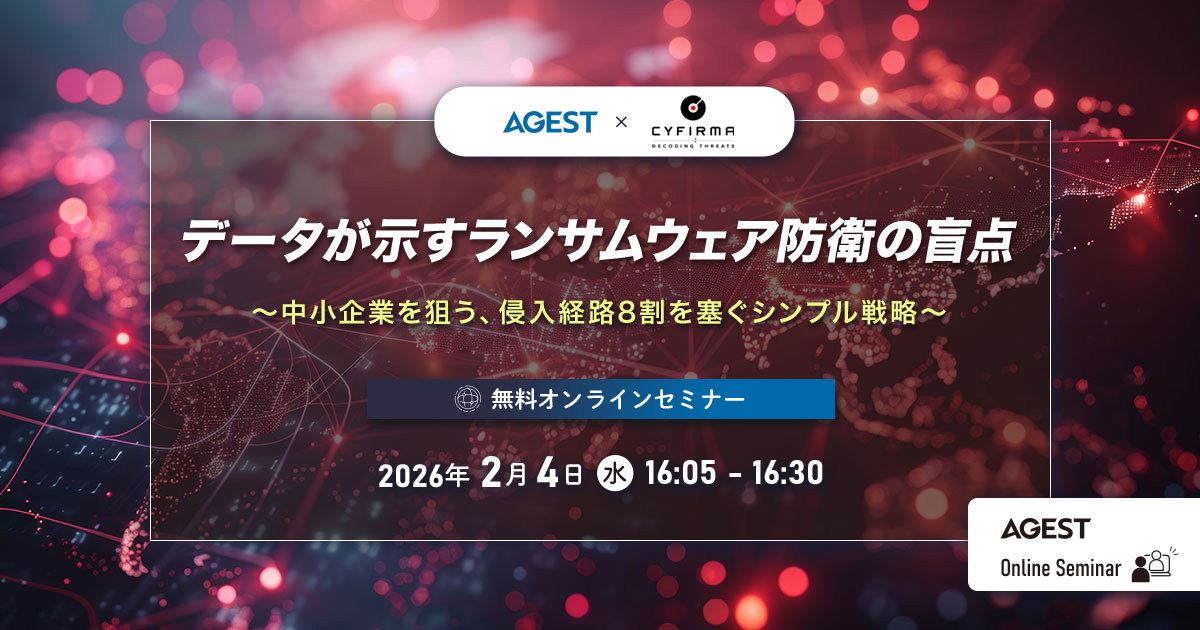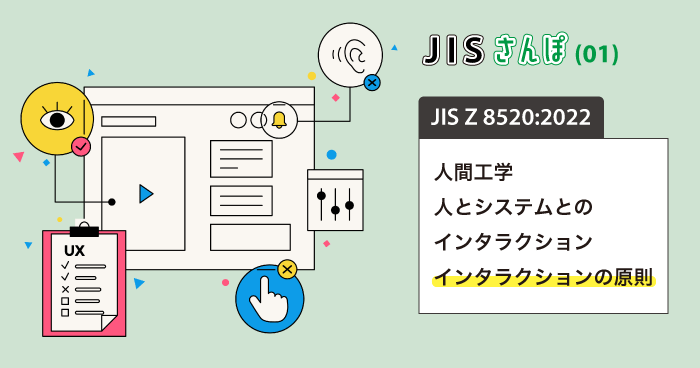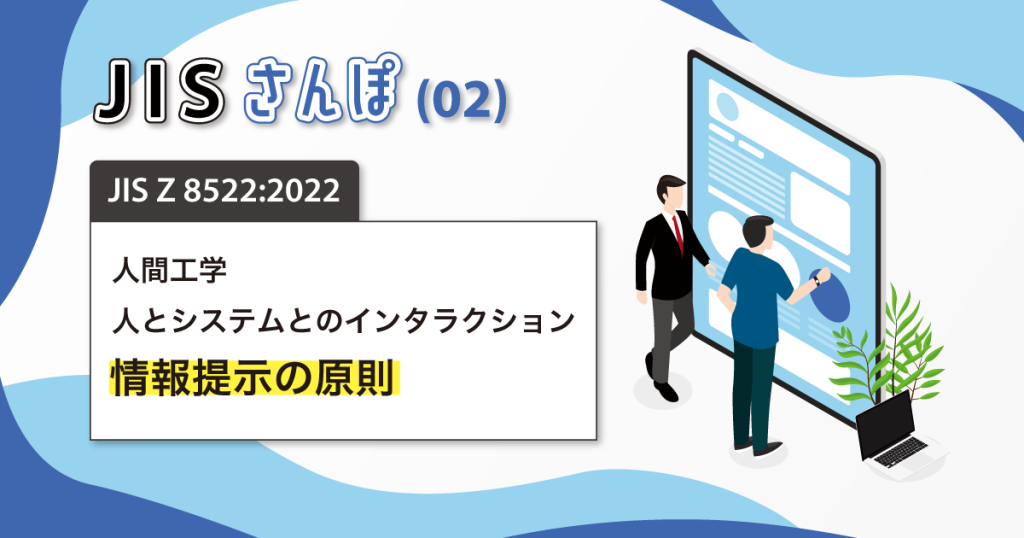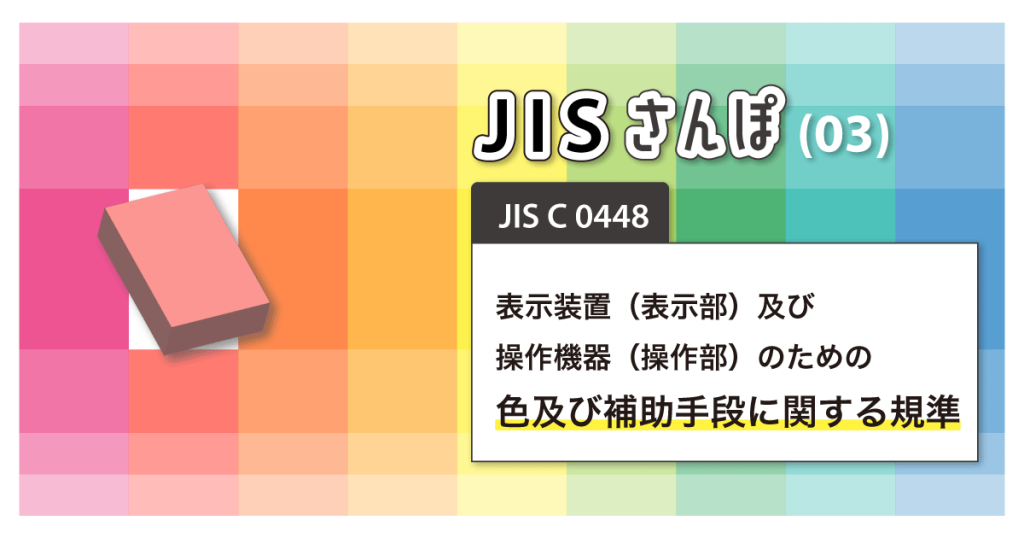
こんにちは、QAコンサルタントのツマミです。
皆さま、JIS※1スキーのツマミが今回目を付けましたのは“色”についてのJISです。我々AGESTの本社前には江戸二大庭園のひとつ、水戸のご老公とも所縁の深い「小石川後楽園」という日本庭園があります。春は枝垂れ桜、初夏は若葉、盛夏は蓮、秋は紅葉、冬は常緑の木々が目を楽しませてくれる素晴らしい日本庭園です。昼休みに窓から「小石川後楽園」とその先に建つ黄色いビルを眺めておりましたところ今回のテーマは“色”が良いのではと思い至りました。
さて、 “色”について言及しているJISは色々ございまして、JIS検索※2で調べますと500件を超え検索不可能と言われてしまいます。規格名称の一部に持つJISに限りましても、なんと144件もの規格がヒットいたします。とはいうもののやはりユーザビリティやアクセシビリティに関連する規格を取り上げたい。
という訳で、次なるさんぽはJIS C 0448「表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準」。今日もまた、ゆるゆると楽しんでまいりたいと思います。
どうぞ皆さま、ちょっとした気分転換としてこのJISさんぽにお気楽にお付き合いの程、よしなに願い奉ります。
※1 JIS:日本産業規格(Japanese Industrial Standards)
※2 JIS検索:https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
▼これまでの「JISさんぽ」はこちら
今回のJIS
JIS C 0448「表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準」とは
この規格は様々な製品やシステムの表示部や操作部に使用する色について規定しています。
色に関する学びを深めるとともに、色だけに頼らないユーザーインタフェース(UI)の構築方法についても学ぶことができる規格となっています。UIを新たにデザインする方、リニューアルを考えていらっしゃる方、不特定多数の方が利用するシステムに携わっていらっしゃる方には是非知っていただきたい規格です。
なぜ、このJISを選んだのか
人間の感覚(視覚、聴覚、触覚など)の内、情報入力においては8割ほどを視覚が担うといわれています。入力情報の内、どの程度を視覚情報から賄っているのかとなると更なる研究が必要だそうですが※3、スマフォアプリやWebシステムのユーザーインタフェース(UI)において視覚情報の比重が高いことは、皆さまも頷いてくださると思います。
であれば、“色”や色の補助手段を知っていることは、UI改善のための強力なツールを手に入れたも同然! と言えるといいなぁ…と思ってこのJISを選びました。
でも、本当に学びの多い規格なんですよ!システムのデザイン標準を策定なさる方は是非一度触れていただきたいJISです。
※3 筑波技術大学テクノレポート Vol.25 (1) Dec. 2017
『「視覚は人間の情報入力の80%」説の来し方と行方』
道行
まえがき、序文
まえがきはシンプルです。「この規格は~日本工業規格である」と紹介されています。前に取り上げたJIS Z 8520、JIS Z 8522とは異なり「この規格が著作権法で保護対象になっている云々」は記載がないですね。1997年版という時代を感じます。
まえがき後半は付属書3件の紹介です。「情報基準の適用例」、「色の補助手段による基準の例」、「電気装置のとっての操作と状態の表示」。“とって”って平仮名で書かれていると分かりづらいですが「取っ手/把手」のことです。この付属書を読んで周りにある“とって”を見渡してみると、なるほどと思うことが多い面白い付属書です。
序文では、この規格がIEC 60073※4を翻訳したものであることが記されています。
なので、この規格に準拠していれば国際的な規格に準拠している※5といえそうです。
※4 IEC:International Electrotechnical Commission 約90か国が参加している
※5 IEC 60073は2002年度版が出ているので、最新版での準拠が必要です。
1章 適用範囲
1章ではこの規格の目的と適用範囲が述べられています。
目的は次の3点。
- 装置を安全に監視したり操作したりすることで、人体、資産、環境の安全性を高める
- 装置の適切な監視、操作、保全を容易にする
- 操作条件や操作部の位置の迅速な確認を容易にする
適用範囲は次のとおり。
- 単一の表示灯、押しボタンから機械や工程の制御装置、制御ステーションまで
(広いですよね! 表示や操作による「マンマシンインタフェース」全般が対象ということです) - 人体、資産、環境の安全が関係する場合、色や補助手段が装置を適切に監視したり操作を容易にしたりするために使用される場合
- 個別の規格で特有の機能に対して固有の識別方法を定めた場合
2章 引用規格
この規格にはJIS C 0447、JIS C 0167という2件のJIS規格が引用されています。
JIS C 0447 「マンマシンインタフェース(MMI)-操作の基準」、操作機器(スイッチやレバーなど)を動かす方向と、動かすことによって機械がどう動くかという関係を統一する規格です。
JIS C 0167 「電気用図記号」、この規格は電気・電子回路の設計図(回路図など)を描く際に使用する記号の形や使い方を定めています。
3章 用語及び定義
ここでは11の用語が定義されています。まず着目したい用語は3.1項の「表示装置(表示部)」。「可視または可聴情報を出す機械的,光学的,電気的又は電子的装置」となっていて、音も対象に入っているという点です。
また、3.2項の「操作機器(操作部)」も本規格の名称に入っている用語ですので着目しておきたい用語です。
備考欄は“ハンドル、とって、押ボタン”などと物理的な形状がある場合に限られるような書き方にも思われますが、注記で「インタラクティブ・スクリーン・ディスプレイの場合にも触れられていてタッチスクリーンのボタン類なども含まれていることが分かります。
他に気になる定義としては「対比(contrast)」。「コントラスト」ではなく「対比」となっているのですが「知覚された明度の対比と対比するように意図された数量」という文章があり、一つの文章の中で若干ニュアンスの異なる対比が使われていて少々おもしろく感じました。
「補助手段」の定義も面白くて、視覚的な補助手段と聴覚的な補助手段があると定義されていますが、どちらにも時間という概念が入っています。確かに、光の点滅や音の断続によって位置や方向、時間的なリミットを示す場合があると思わず頷いてしまいました。自分で定義を考えたらヌケモレしそうな要素です。
4章 一般要件
4章は色を使うときに必要な要素や条件が示されています。
4.1 基準の原則
4.1項ではユーザビリティで非常に重要な要素だとツマミが考えている「統一性」について述べられています。つまり(色の使い方や点滅の仕方などについての)規準となる原則は同じプラントや工程内の他の装置の原則と一致させましょうと書かれています。しかもその規準をシステム設計の初期段階で制定しましょうとも書かれています。
その上で色相(色合い、赤・黄・緑・青など)と点滅の規準については色の持つ意味を一貫させ、最優先としたい情報のために使用するようにと言ってきているわけですね。
更に表1と2で決めるべき要素はこれとこれですよと示してくれています。
主要素である「色」は色相、彩度(色の鮮やかさ)、明度(明るさ/暗さ)、対比(コントラスト)の4要素があがっています
因みにコントラストはアクセシビリティに影響するので、デザイン標準を作成なさる方は是非JIS X 8341-3の達成基準である4.5:1を思い出して欲しいところです。
色だけではなく補助手段や文字の表記も使用を勧められています。特に色覚に違いのある方のことも考慮して色だけを基準の手段としないよう、補助手段の併用が推奨されています。
その補助手段は色と同じ視覚情報として「形状、位置、時間」があげられており、聴覚情報として「音の種類、周波数、時間」があげられています。「音」の要素って「音色、音程、音の大きさ」だとツマミは思っていたのですが、この規定では「音色」がさらに細分化され「音色、雑音、言葉」となっています。補助手段としての「雑音」って何なのだろうと思いましたが附属書Bに参考例として「ノック音」が入っており、注意を喚起する音として例えば単音でもなく和音とも言えない音使いを「雑音」と表しているのかなと思いました。
他の要素も「音程」は計測、再現しやすいよう「周波数」として定義するようになっていますし、「音の大きさ」は「時間」の中の「音圧レベルの変化超過時間」という言葉で定義されていて規格っぽい感じを受けます。
4.2 色による基準
本項の冒頭で「色は,注意を喚起するために最も有効な手段である。」と述べられています。
また、特定の色には特定の意味を割り付けること、実際に使用する特定用途の色数を最小限にすることが推奨されています。この規格でも説明は「赤、黄、緑、青、黒、灰、白」の7色だけに絞り込んでいます。
4.3 色の選定
本項では、まず色の意味についての一般原則が「人体又は環境の安全」、「工程の状態」、「装置の状態」に分けて次のように定義されています。
| 色 | 人体または環境の安全 | 工程の状態 | 装置の状態 |
|---|---|---|---|
| 赤 | 危険 | 非常(緊急) | 一般的な意味づけは無い |
| 黄 | 注意 | 異常 | |
| 緑 | 安全 | 正常 | |
| 青 | 強制的な意味 | ||
| 黒、灰、白 | 特別な意味づけは与えていない | ||
デザイン標準などでは上記表に記載の意味に従って色使いの規準を定めていくわけですが、後述の3つの表※5の間で意味の混乱が起きず、しかも色の意味に従った内容で明確に決定する必要があると記載されています。
なお、本項ではビデオ・ディスプレイ・スクリーン上の表示色についても言及されています。「各色に割り付けされた意味は,ディスプレイ内で調査していること」と、割と難しめのオーダーがサラッと書かれています。
※5 後述の3つの表
表4:「人体,資産及び/又は環境の安全に関して表示装置(表示部)の色が表す意味」
表5:「工程の状態に関して表示装置(表示部)の色が表す意味」
表6:「表示装置(表示部)の好ましいとされる色が装置の状態に関して表す意味」
4.4 点滅表示による情報の規準
点滅表示は通常より注意を惹きたい場合に使うなど、点滅表示を使う状況や状態が定められています。点滅状態はゆっくり目と通常の点滅の2つのモードがあり、1つのモードしか使わない場合は通常の点滅を使う必要があるようです。
ゆっくり目と通常の点滅は、もちろん周波数で定義されています。
- ∫1:ゆっくりとした点滅。 0.4Hz~0.8Hz(24~ 48点滅/1分間)
- ∫2:通常の点滅。 1.4Hz~2.8Hz(84~168点滅/1分間)
心拍数が通常60~100回/1分間なので通常の点滅でも結構早目な感じがしませんか。
更に本項では点灯と滅灯の時間比を1:1にすることや、ゆっくり目の点滅(∫1)と通常の点滅(∫2)の周波数の比を∫1:∫2=1:4(例 0.5Hz:2.0Hz)にすることが推奨されるなど学びの多い項となっています。
4.5 補助手段に使用する色
本項はあっさりとしていて、安全性に関わる用途で色の基準を決める場合は他の補助手段の基準で補足することが定められています。安全にかかわる場合、色だけで判断しようとして誤解が生じると取り返しのつかない障害になる場合も考えられるので、補助手段の利用は納得の極みです。
5章 表示装置(表示部)
5.1 使用形態
表示装置(表示部)の表示は装置の状態に関する情報を提供すること、操作員に対しては注意を喚起したり、次にどうすればよいかに関する情報を表示したりすることが述べられています。
そして具体的な例として次の3表が掲載されています。
表4:「人体,資産及び/又は環境の安全に関して表示装置(表示部)の色が表す意味」
表5:「工程の状態に関して表示装置(表示部)の色が表す意味」
表6:「表示装置(表示部)の好ましいとされる色が装置の状態に関して表す意味」
5.2 機械的表示装置(表示部)への特別要件
機械的表示装置(表示部)の表示について、図記号や色の要件が述べられています。
6章 操作機器(操作部)
操作機器(操作部)に使用する色についてかなり詳細に述べられています。
非照光式操作機器(操作部)と照光式操作機器(操作部)については、是非、本規格や関連規格を読み込んで使用する色の基準、位置や形状を定めてください。
ビデオ・ディスプレイ・スクリーン上の画像表示の一部としての操作機器(操作部)についても6.3項で述べられている「非常(緊急)操作に備えて, ビデオ・ディスプレイ・スクリーン上に再生する操作機器(操作部)は,操作員が作業及び操作をしている位置から,指定されている時間に見ることができ,かつ,利用しやすいこと」の意味を熟考して画面をデザインください。
附属書A(参考) 情報基準の適用例
「試験所に連結した表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)の表示」
例として表示機器や操作機器がどのように配置されているか示した図を用いて、どのスイッチはどの色でなければいけないか、補助手段が必要かといったことが説明されています。本文で示された基準をどのように用いるのかの参考となる例だと思います。
附属書B(参考) 色の補助手段による基準の例
補助手段にどのようなものがあって、どのように使うのかといったことの手がかりとなる例が示されています。特に補助手段としての可聴符号例は表示部や操作部が見えない場合(夜間、煙の中などといった状況下も考えられます)の解決手段のヒントになるのではないでしょうか。
附属書C(参考) 電気装置のとっての操作と状態の表示
この付属書Cはネガティブな操作(N操作:より消極的方向への操作)とポジティブな操作(P操作:より積極的方向への操作)がどういったものであるのかが学べてツマミ的には楽しい読み物となっています。また、操作を言語で表す際の定義や様々なとって(把手)、スイッチの形状と操作方向が図で示されています。全部で25ページある本規格の約1/3(9ページ)が割かれていて大変読み応えのある附属書です。
以上がJIS C 0448「表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準」となります。
今日見つけた宝物
「人体、資産、環境の安全性を高める」
この宝物はJISの第1章「適用範囲」の第1項にあります。操作者や周りの方々が咄嗟の時でも安全に操作できるよう知恵を重ねてきた先人たちの努力が伺えます。UI設計に携わる方でも、直接本規格に準拠する必要のある方は少数だと思いますが、このような基準があることを知っておき色の使い方の原則を崩さないUI設計を心掛けてくださればと願います。
さてさて今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。本日の道行きはいかがでしたでしょうか。次のさんぽは今度こそJIS S 0137「消費生活用製品の取扱説明書に関する指針」にしたいと思っております。全く別のJISになった場合も、そこは気まぐれな道行き、是非ご一緒くださいますようお願いいたします。