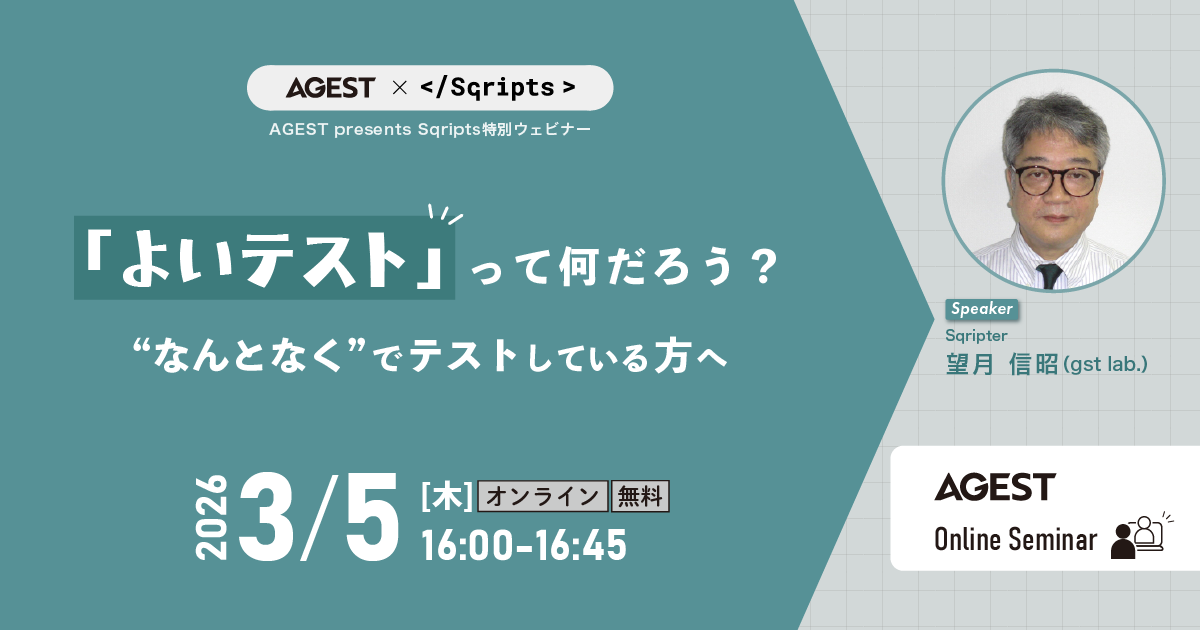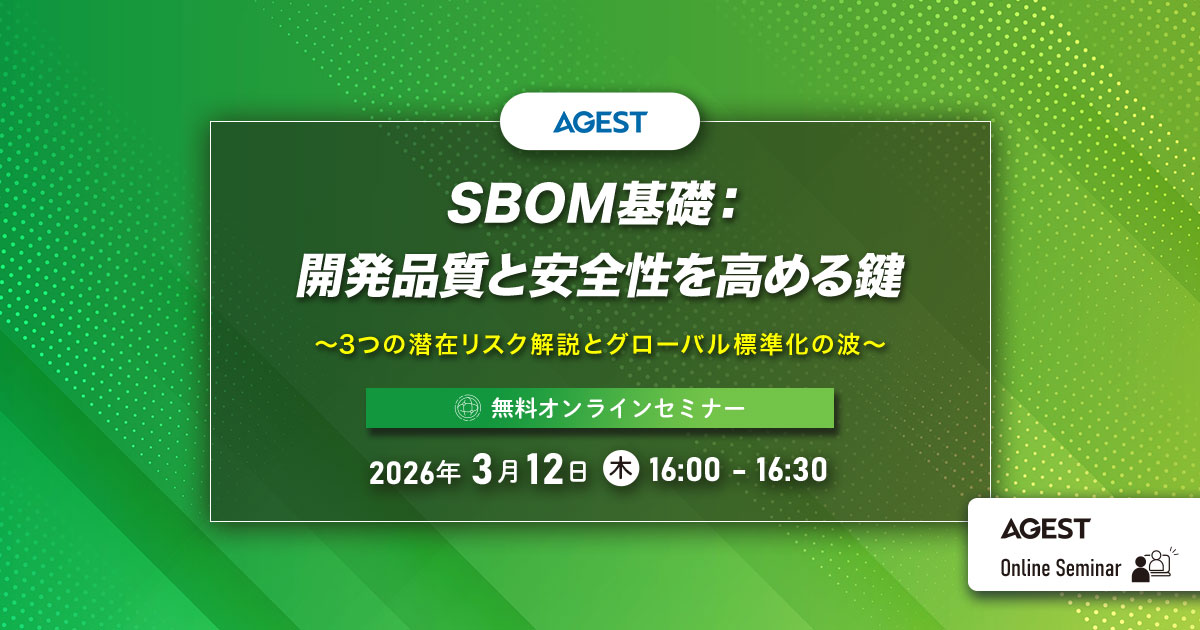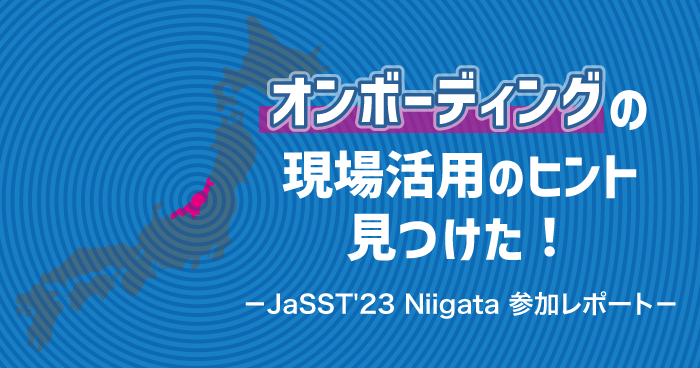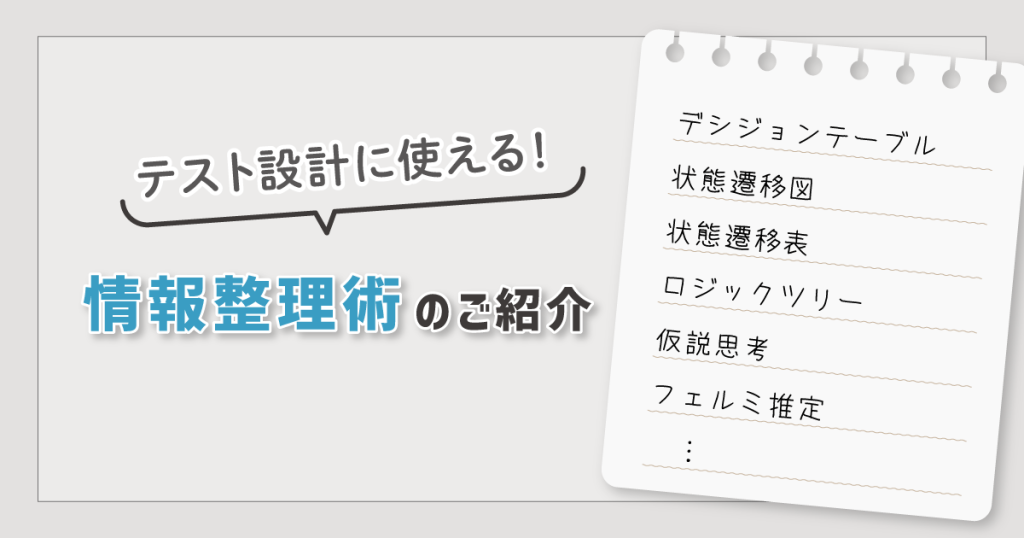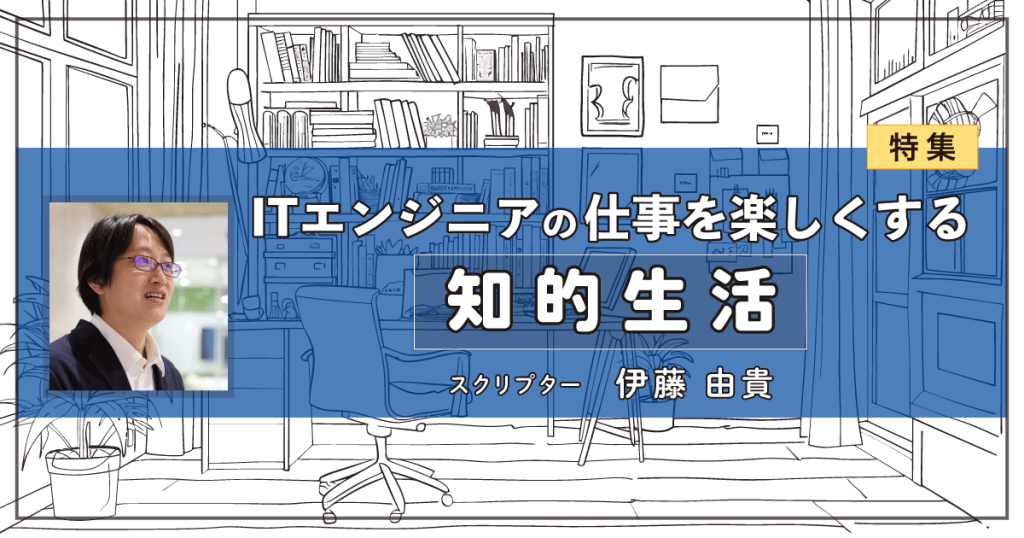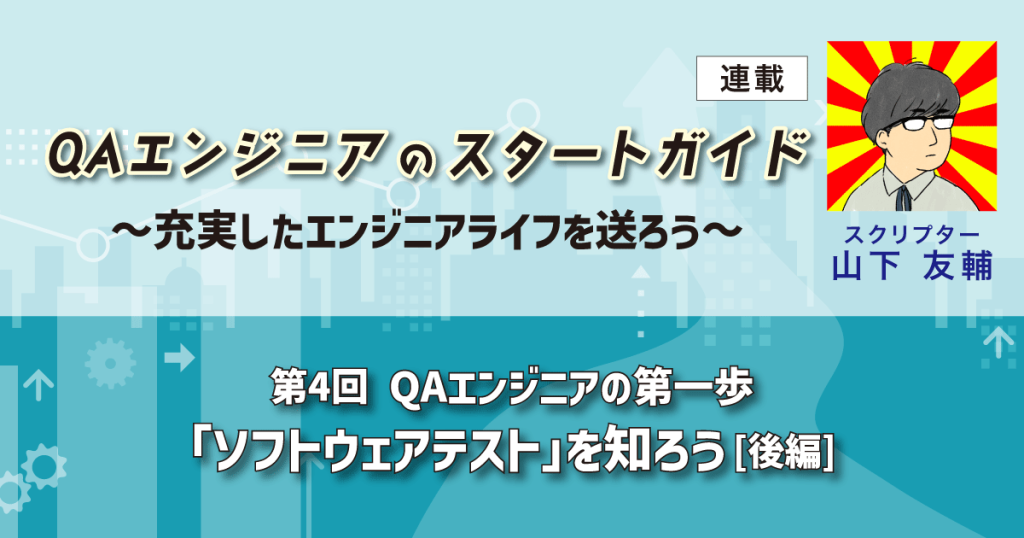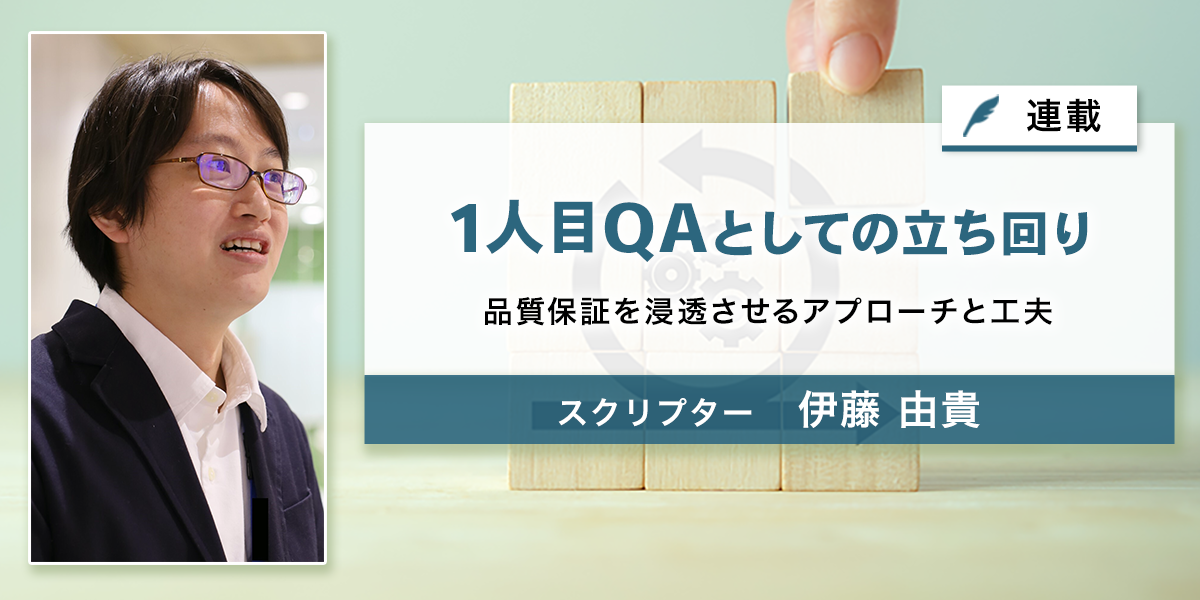
1人目QAとしての立ち回り、第3回となる今回は、QAエンジニアや品質保証のことを開発組織に知ってもらうための取り組みについてご紹介します。
前回の記事では、1人目のQAは開発組織に対して品質文化を浸透させる役割を求められる、と書きました。しかし、「文化の浸透」という大きなことを、一足飛びに実現するのは困難です。
「品質のことを考えよう」「改善活動を行おう」と組織全体に訴えかける前に、まずは品質やQAエンジニアについて、知ってもらうところから始めることが大切です。
<1人目QAとしての立ち回り 連載一覧>※クリックで開きます
【第1回】1人目QAの位置づけと、開発組織へのアプローチの仕方
【第2回】組織に品質保証を浸透させるアプローチ
【第3回】品質保証やQAエンジニアを知ってもらうための取り組み
【第4回】1人目QAのスタートは開発組織の現状把握から。やるべきこと・把握すべきこと。
【第5回】1人目QAアンチパターン
QAエンジニアという“異分子”
1人目QAとして開発組織に加わった場合、周りの開発者からみると、QAエンジニアは「謎の存在」あるいは「異分子」と表現してもいいかもしれません。
いったい何をする存在なのか、居ることによって自分たちにどのようなメリットがあるのか、などが不明確な状態です。
もし中途として採用されたのであれば、組織のトップや一部のマネージャーなどは、QAエンジニアの存在意義や行動についてなんらかの期待をもっているでしょう。あるいは、社内でのジョブチェンジとしてQAエンジニアになった場合も、なんらかのミッションを負っているはずです。つまり、1人目QA本人は、すくなくともぼんやりとは「何をする人なのか」をわかっているはずです。
しかし、周囲はそうではありません。もしかしたら「前職でQAエンジニアにあまり良い印象がなかったんだよね」とか、「テストしてくれる人でしょ?」なんてイメージを持っている可能性すらあります。
「相手はわかってくれているはずだ」という思い込みがキケンなのは、QAエンジニアに限らずお仕事の基本です。そのため、1人目QAは自分自身が「謎の存在である」という気持ちで、周りに認知されるよう動くことが必要です。
開発組織に認知してもらうには
周囲に認知してもらうために1人目QAができることはいろいろとあります。ここでは、私自身が1人目QAとして行ったことや、周囲のQAと情報交換をする中で複数人が実践していた方法について説明します。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。