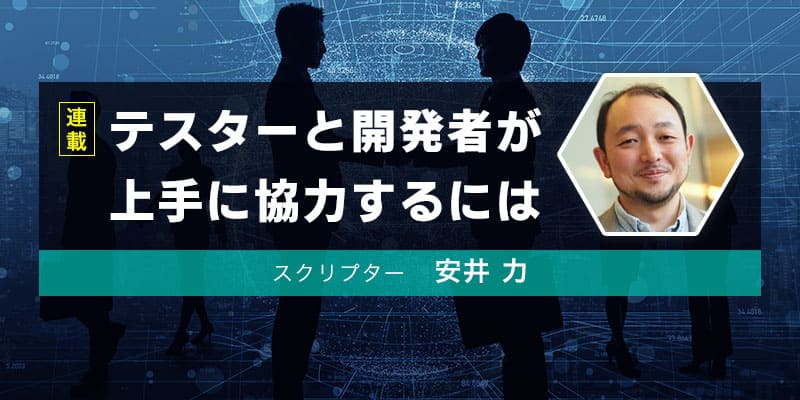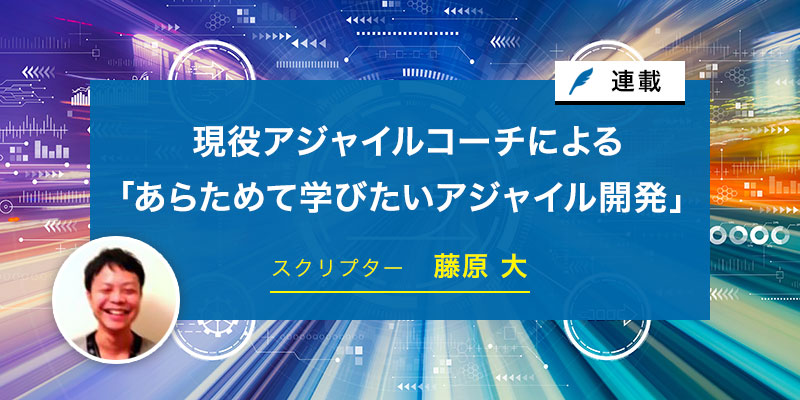
この連載は、登場して20年が過ぎ、成熟期を迎えつつある「アジャイル開発」を解説します。アジャイル開発については、世の中にたくさんの書籍や情報があふれていますが、アジャイルコーチとして10年以上の現場経験をもとに、あらためて学び直したい情報を中心にまとめていきます。
第13回目のテーマは、「かんばん」です。
この内容はUdemyで公開しているオンラインコース「現役アジャイルコーチが教える!半日で理解できるアジャイル開発とスクラム 入門編」の内容を元にしています。
かんばんの誕生
かんばんは、イギリス人のデイヴィッドさんが考え出した開発手法です。
かんばんはその名の通り日本語が元になった開発手法です。もともとはトヨタ生産方式で使われているかんばんがベースなのですが、トヨタのかんばんとこのかんばんは、思想は似ていてもまったく異なる手段です。
かんばんは、開発手法としてのかんばんと、ツールとしてのかんばんがあります。開発手法のかんばんは、XPやスクラムのようなもので、原則が手順書のようになっているのではじめやすく、誰にでも理解しやすくなっています。
ツールとしてのかんばんは、タスクをふせんではりつけたタスクボードをさしています。厳密に言うとタスクボードとかんばんはちょっと違うのですが、このあたりも後ほど解説します。
かんばんに関しては、自分が翻訳した書籍『リーン開発の現場』をベースに解説します。また、翻訳の際に、かんばんの英語版Wikipediaページも日本語に翻訳しました。こちらもかんばんの理解にとても役立つ内容なので、おりまぜて解説します。
かんばんの基本原則
まず、かんばんの基本原則を解説します。
解説と言っても、原則自体が文章になっているので、これまでの開発手法とちがってとてもわかりやすい内容になっています。
原則: 現在、何をしているかを理解することから始める
ひとつめは「現在、何をしているかを理解することから始める」です。
続きを読むにはログインが必要です。
ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。